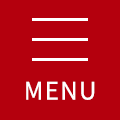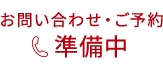心臓弁膜症とは
 心臓弁膜症とは、心臓を構成する4つの部屋 (右房、左房、右室、左室)を隔てている弁が適切に働かなくなる病気です。大動脈弁、僧帽弁、三尖弁、肺動脈弁の4つの弁にそれぞれ狭窄症と閉鎖不全症があります。一般的に、弁が閉じずに血液が逆流を起こした状態を閉鎖不全症、逆に弁が狭くなって血流を阻害している状態を狭窄症と言います。
心臓弁膜症とは、心臓を構成する4つの部屋 (右房、左房、右室、左室)を隔てている弁が適切に働かなくなる病気です。大動脈弁、僧帽弁、三尖弁、肺動脈弁の4つの弁にそれぞれ狭窄症と閉鎖不全症があります。一般的に、弁が閉じずに血液が逆流を起こした状態を閉鎖不全症、逆に弁が狭くなって血流を阻害している状態を狭窄症と言います。
弁の機能が低下すると、心臓が全身に十分な血液を送り出せなくなり、心臓の動きの低下、不整脈の出現、心不全などの問題が生じてきます。
考えられる原因としては、加齢や高血圧による動脈硬化、心筋梗塞、心筋症などがありますが、生まれつきの先天的な疾患も挙げられます。
心臓弁膜症は実は「隠れ心不全」?
心臓弁膜症は自覚症状に乏しい特徴があり、気づかないうちに発症・進行していることが多いことから、隠れ心不全とも呼ばれています。また、心臓弁膜症の検査や治療には専門的で高度な知識や技術が必要なため、診療できる医療機関も限られています。
当院では、循環器専門医である院長が心臓弁膜症の診療を行っています。また、豊富な経験と知識によって、患者さま一人一人に最適な治療方針を検討することが可能です。
健診などの心電図検査や胸部レントゲン検査で異常を指摘された場合や、気になる症状が現れている場合には、できるだけ早めに当院までご相談ください。
心臓弁膜症の種類
大動脈弁狭窄症
大動脈弁狭窄症とは、加齢や高血圧などが原因で大動脈弁が石灰化し、開きにくくなる病気です。大動脈弁が適切に開かなくなることで血流が滞るようになり、心不全や突然死など重篤な症状を引き起こします。
中には、無症状でも重度な場合があり、治療ではカテーテル手術や外科手術を行うことがあります。
大動脈弁閉鎖不全症
大動脈弁閉鎖不全症とは、血管の異常や弁の構造上の異常により弁が適切に閉じなくなり、血液が逆流を起こす病気です。主な症状は、動悸や息切れ、疲労、倦怠感などで、進行すると心臓の拡大と共に、心臓の機能が低下し、心不全を引き起こす恐れがあります。
僧帽弁狭窄症
僧帽弁狭窄症とは弁が癒着するような形で適切に開かなくなる病気です。僧帽弁が適切に開かなくなることで血流が滞るようになり、心不全による重篤な症状を引き起こします。また心房細動を引き起こすリスクが高いです。僧帽弁狭窄症の原因は幼少期のリウマチ熱への罹患が言われていましたが、近年では抗菌薬の普及により患者数は減少し、多くは透析患者さまとなっています。
僧帽弁閉鎖不全症
僧帽弁閉鎖不全症とは、僧帽弁が適切に閉じなくなることで血液が逆流を起こす病気です。進行すると、心臓の拡大と共に、心臓の機能が低下し、心不全を発症します。また心房細動を引き起こすリスクがあります。僧帽弁閉鎖不全症には僧帽弁に構造的な異常がある器質性僧帽弁閉鎖不全症と、僧帽弁に器質的な異常はないが、心筋の拡大による機能性僧帽弁閉鎖不全症があります。治療法はカテーテル治療と外科的手術があります。
三尖弁閉鎖不全症
三尖弁閉鎖不全症とは、三尖弁が適切に閉じなくなり、心臓から右房へ血液が逆流する病気です。逆流によって右心室の負担が増大し、右心不全を引き起こす恐れがあります。
主な症状は、腹部の張りや下半身のむくみ、食欲減退などが挙げられます。
心臓弁膜症の原因
先天性異常
心臓弁膜症の原因の一つに、先天性の異常が考えられます。先天的に心臓弁の数や形状、厚み、弾力性に異常が生じることで様々な心臓弁膜症を引き起こす恐れがあります。
炎症や感染症
炎症や感染症などの病気によって心臓弁に障害が起きると、心臓弁膜症を引き起こすことがあります。代表的な病気として、感染性心内膜炎やリウマチ熱などが挙げられます。
加齢による変化
加齢によって心臓弁膜が硬化する退行性変化を起こすと、柔軟性が低下して弁が適切に開閉しなくなり、心臓弁膜症を引き起こします。
心疾患によるもの
心筋梗塞、拡張型心筋症などの心疾患を起こすと、心臓全体もしくは一部が拡大します。その結果、心臓の弁自体には異常が無いにもかかわらず、弁同士が離れてしまい、閉鎖不全症を引き起こします。
心臓弁膜症の症状
心臓弁膜症は、初期の段階では自覚症状に乏しいために気づかないことが多く、病状が進行すると、心臓の負担が増大して様々な心不全に症状が現れるようになります。そのため、心臓弁膜症は隠れ心不全とも呼ばれています。
主な症状は、動悸や息切れ、呼吸困難、下半身のむくみなどで、更に進行すると心房細動や不整脈を合併する恐れもあります。
心臓弁膜症の検査
心臓弁膜症の検査は、高度な循環器系の専門知識が必要になるため、診療できる医療機関は限られています。
当院では、経験豊富な循環器専門医である院長が検査を担当しますので、高精度な検査が可能です。ご希望の際にはぜひ当院までご相談ください。
心臓弁膜症の主な検査は以下となります。
聴診
心臓弁膜症を発症すると、聴診した際に、弁の異常から特徴的な雑音が聞こえることがあります。心周期の中で心雑音が聞こえるタイミングや聴取される胸部の位置によって弁膜症の種類を判定します。
心電図検査
心電図検査は、心臓弁膜症の確定診断を行う際に有効な検査です。心臓弁膜症を発症すると、心電図検査の際に特徴的な波形パターンが現れます。
エコー検査
心臓弁膜症を確定診断する上で最も有効な検査が、心エコー検査です。心エコー検査は、超音波を胸部に照射することで心臓の構造や機能を確認でき、心臓弁の形状や開閉の有無、血流の状態などを詳細に把握することが可能です。
心臓カテーテル検査
心臓カテーテル検査とは、血管の中にカテーテルを挿入して心臓まで誘導し、心臓の中の圧力を直接計測してくる検査です。心内圧を測ることで心臓弁膜症の重症度を評価します。また心臓に造影剤を注入することで心臓内での血液の逆流の度合いなども確認できます。
なお、心臓カテーテル検査が必要と判断した場合は、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
心臓弁膜症の治療
 心臓弁膜症は、症状の程度によって治療の必要がなく経過観察に留める場合や、早急に治療が必要な緊急性の高い場合など様々です。
心臓弁膜症は、症状の程度によって治療の必要がなく経過観察に留める場合や、早急に治療が必要な緊急性の高い場合など様々です。
治療には薬物療法と手術療法があり、初期の段階では、薬物療法によって症状を改善させることができます。しかし心臓弁膜症の種類や重症度によっては手術療法が必要となります。手術療法と聞くと怖い気持ちになるかと思いますが、現在ではカテーテル治療という開胸を必要としない治療法やMICSという小さい傷で手術をする方法があります。これらの治療は実施できる医療機関が限られてきますので、当院では患者さまに最適な治療法を提案させていただき、その治療法を提供できる高度医療機関に責任を持ってご紹介いたします。
心臓弁膜症は薬物治療とするか手術療法とするかの判断や手術療法を行うタイミングの判断が非常に難しいご病気です。自分が心臓弁膜症ではないかと心配な方や、すでに心臓弁膜症と診断されていても、治療法について専門家にご相談されたい方はお気軽に当院までご相談ください。
薬物療法
薬物療法では、心不全の治療法に準じた薬物を、患者さまの心臓の機能に合わせて選択していきます。
手術療法
心臓弁膜症は、ある一定の重症度に達すると薬物治療を行っていても、心臓の機能は低下していきます。そのため症状が軽度であっても、心臓の機能障害が進行しきってしまう前に手術療法を行っていきます。手術療法にはカテーテル治療と外科的手術があります。カテーテル治療は開胸をしないために比較的に低侵襲な治療となります。外科的手術は、弁形成術と弁置換術の2種類があります。また外科的手術においてもMICSという小さい傷のみで侵襲を抑えた手術方法もあります。なお、手術療法が必要と判断した場合は、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。