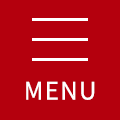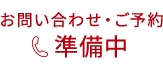呼吸器疾患とは
呼吸器は、鼻や喉から始まり、気管、気管支、肺へと続く空気の通り道です。この通り道に問題が生じている場合を呼吸器疾患と言います。「上気道」と「下気道」に分かれ、上気道では、喉の炎症(咽頭炎・扁桃炎)や、寝ている間に呼吸が止まる「睡眠時無呼吸症候群」などの病気が起こります。下気道では、気管支炎、肺炎、結核、喘息、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、肺がんなどがあります。
当院では、これらの病気を調べて診断し、適切な治療を行います。症状が重い場合や、肺がん・結核など専門的な治療が必要な場合は、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
呼吸器疾患でよくある症状
- 咳で目が覚める
- 咳が続く(長引いている)
- 夜間や早朝に咳がひどくなる
- 横になると咳が出る
- 痰が出る・痰が切れにくい
- 痰の色が変わっている(黄色・緑色など)
- 血が混じった痰(血痰)が出る
- 息切れがする・呼吸が苦しい
- 横になると息苦しい
- 胸が痛む(深呼吸や咳で悪化)
- ゼーゼー・ヒューヒューと音がする(喘鳴)
- 家族にいびきを指摘された
- 睡眠中に呼吸が止まると言われた
- 日中の強い眠気
- 慢性的な疲労感
- 発熱がある
など
よくある呼吸器疾患
- 気管支喘息
- 咳喘息
- 慢性気管支炎
- 慢性閉塞性肺疾患(COPD)
- 細菌性肺炎
- 間質性肺炎
- マイコプラズマ肺炎
- 肺結核
- 肺がん
- 肺気腫
- 気胸
- 睡眠時無呼吸症候群
- インフルエンザ
- 新型コロナウイルス
- RSウイルス感染症
- 百日咳
- 慢性呼吸不全
- 職業性肺疾患(じん肺・アスベスト肺など)
など
気管支喘息
気管支喘息とは、たばこの煙やホコリ、ダニなどのアレルゲンを吸い込んだり、ストレスを溜め込んだりするなどが原因で気道に炎症を引き起こす病気です。炎症を起こすことで気道が狭くなり、咳や呼吸困難などの症状が現れます。
主な治療は、炎症を抑えて気道を広げるための薬物療法となります。
咳喘息
咳喘息は喘息の一種で、主な症状は長引く咳ですが、通常の喘息にみられる喘鳴はほとんどありません。夜間や早朝に咳が悪化しやすく、特にアレルギーや風邪の後に発症することが多いです。治療には吸入ステロイドや気管支拡張薬を使用し、適切な治療を行わないと、気管支喘息へ進行するリスクがあります。
慢性気管支炎
慢性気管支炎は、咳や痰などの症状が1年のうち3ヶ月以上持続し、この状態が2年以上継続していること、かつ他の病気の可能性を除外できることで確定診断となります。慢性的な粘り気のある痰を伴う咳が特徴で、悪化すると肺炎によって発熱などの症状が現れることがあります。
慢性閉塞性肺疾患(COPD)
慢性閉塞性肺疾患(COPD)とは、肺の中の気管支に慢性的な炎症が起きることで気管支の狭窄と、肺胞壁の障害が生じ、咳や痰、呼吸困難などの症状を引き起こす病気です。主な原因は喫煙で、喫煙習慣がある人の15~20%が発症しているという報告もあります。慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、病態によって慢性気管支炎と肺気腫の2種類に分類されます。気管支の炎症のみの場合は慢性気管支炎と診断されますが、呼吸機能を司る肺胞が破壊されると、肺気腫と診断します。
細菌性肺炎
肺炎は2023年の死因で第5位にランクインしており、その多くが細菌性肺炎です。特に高齢者や持病がある方が発症しやすいです。最も一般的な原因菌は肺炎球菌で、この菌に対してはワクチン接種が有効です。
主な症状は発熱、咳・痰、息苦しさで、抗生物質による治療が効果的ですが、重症化すると入院が必要になることもあります。風邪だと思っていたら肺炎だったということもあるので、熱や咳・痰が長引いたり、息苦しさがあれば早めに受診してください。
間質性肺炎
間質性肺炎は、肺の間質部分に炎症や瘢痕が生じる病気です。原因が不明なことが多く(特発性間質性肺炎)、喫煙、感染、自己免疫疾患などが原因となることもあります。主な症状は息切れや乾いた咳で、病気が進行すると肺機能が低下します。治療は原因によって異なり、ステロイドや免疫抑制剤、抗線維化薬が使用され、重症の場合は在宅酸素療法が必要となることもあります。
マイコプラズマ肺炎
マイコプラズマ肺炎は、マイコプラズマという細菌が原因で起こる肺炎です。特に若い人に多く、主な症状は発熱、乾いた咳、倦怠感です。咳が長引くことが多いです。抗生物質で治療でき、早めに治療を始めれば症状の悪化を防げます。
肺結核
肺結核は、結核菌という細菌が原因で起こる感染症です。主な症状は長引く咳、血が混じった痰、発熱、夜間の発汗、体重の減少などです。特に免疫力が弱っている人が感染しやすいです。治療には抗結核薬が使われますが、途中で治療を中断すると、お薬に耐性を持った菌が出てきて、治療が難しくなることがあります。早期に診断して治療を始めることが大切です。結核の疑いがある場合は、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
肺がん
肺がんは、肺に発生する悪性腫瘍で、喫煙が主なリスク要因です。初期には症状が乏しく、進行すると咳、血痰、胸痛、息切れ、体重減少が見られます。非小細胞肺がんと小細胞肺がんの2種類があり、治療には手術、放射線治療、化学療法、免疫療法などがあります。早期発見が予後を大きく左右します。肺がんが疑われた際は、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
肺気腫
肺気腫とは、喫煙などが原因で体内の呼吸機能を司っている肺胞が破壊される病気です。肺胞は酸素の吸収と二酸化炭素の排出を行う働きがあるため、肺気腫になると咳や痰の他、息の吐き出すことが困難になる閉塞性障害といった症状を引き起こします。
気胸(肺気胸)
気胸は、肺の一部が破れて空気が胸腔内に漏れ、肺がしぼんでしまう状態です。典型的な症状は突然の胸痛や呼吸困難です。自然気胸(特に痩せ型の若年男性に多い)や外傷性気胸などがあります。軽症の場合は自然治癒することもありますが、重症の場合は胸腔ドレナージや手術が必要となることがあり、必要に応じて連携する医療機関をご紹介いたします。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群は、睡眠中に気道が閉塞し、呼吸が断続的に止まる病気です。主な症状には、いびき、日中の強い眠気、集中力の低下などがあり、肥満や首周りの脂肪蓄積が原因となることが多いです。診断には自宅でできる簡易型終夜睡眠ポリグラフ検査がまず行われ、結果により精密検査が必要と判断された場合は、入院しての終夜睡眠ポリグラフ検査が行われます。治療方法としては、CPAP(持続陽圧呼吸療法)や減量、生活習慣の改善が推奨されています。
インフルエンザ
インフルエンザは、毎年11月から3月にかけて流行する感染症です。感染すると、突然38℃以上の高熱、頭痛、咽頭痛、咳、鼻水、全身倦怠感、関節痛、筋肉痛などの風邪に似た症状が現れます。インフルエンザは軽視されがちですが、特に子どもが感染すると、まれに急性脳症を引き起こしたり、高齢者や免疫力が低下している人が感染すると肺炎など重症化する可能性があるため、十分な注意が必要です。
新型コロナウイルス感染症
新型コロナウイルス感染症は、新型コロナウイルスに感染することで発症する病気です。主な症状には、38℃以上の発熱、頭痛、咽頭痛、咳、鼻水、全身倦怠感、関節痛、筋肉痛などがあります。風邪やインフルエンザと似た症状が現れますが、感染してから数日間の潜伏期間を経てから発症することが多いため、その間に周囲に感染を広げてしまう可能性があります。