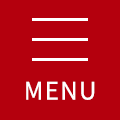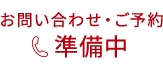動悸・息切れとは
動悸とは
 動悸とは、自分の心拍の鼓動を感じる状態です。血圧や脈拍数が正常でも、普段よりも強い心臓の鼓動を感じたら動悸と判断できます。
動悸とは、自分の心拍の鼓動を感じる状態です。血圧や脈拍数が正常でも、普段よりも強い心臓の鼓動を感じたら動悸と判断できます。
動悸が生じる原因は様々であり、原因疾患によって症状や程度も異なります。主な原因は、貧血や甲状腺の病気、心臓系の病気、不整脈、ストレスといった心因的要因など様々です。検診などの心電図検査の最中に動悸が起きれば確定診断となりますが、動悸が現れるタイミングは不規則であることが多く、検査中に症状が現れない場合には、見逃されてしまうこともあります。
治療は原因疾患によって異なります。軽度な場合は、治療の必要がないこともありますが、動悸とともに息切れや胸痛、胸の圧迫感などの症状を併発している場合は、心不全や虚血性心疾患など重篤な病気が隠れていることもあるため、精密検査によって詳しい状態を確認し、適切な治療を開始することが大切です。
息切れとは
息切れとは、普段は無意識に行っている呼吸を、意識的に行わないと息苦しさを感じる状態です。
激しい運動の直後に息切れを起こすのは普通ですが、階段の上り下りなど軽度な運動の際にも息切れを起こす場合は、何らかの病気が関与している可能性があります。
息切れの評価方法
息切れの程度を評価する基準として、MRCスケール(Medical Research Council dyspnea scale)があります。具体的な評価基準は以下となります。
| 症状 | |
| Grade0 | 息切れを感じない |
| Grade1 | 強い労作で息切れを感じる |
| Grade2 | 平地を急ぎ足で移動する、または緩やかな坂を歩いて登るときに息切れを感じる |
| Grade3 | 平地歩行でも同年齢の人より歩くのが遅い、または自分のペースで平地歩行していても息継ぎのため休む |
| Grade4 | 約100ヤード(91.4m)歩行したあと息継ぎのため休む、または数分間、平地歩行したあと息継ぎのため休む |
| Grade5 | 息切れがひどくて外出ができない、または衣服の着脱でも息切れがする |
動悸・息切れの原因
動悸・息切れを引き起こす原因は様々です。主な原因は以下となります。
心臓の異常
不整脈や心筋症、心臓弁膜症などの心疾患を発症すると、動悸や息切れを起こすことがあります。
呼吸器の異常
喘息や肺炎、慢性閉塞性肺疾患(COPD)などの呼吸器系の病気を発症すると、呼吸機能が乱れて動悸や息切れを起こすことがあります。
代謝異常
甲状腺機能亢進症や副腎疾患などの代謝系の病気を発症すると、動悸や息切れを起こすことがあります。
不健康な生活習慣
脂質の多い食事や肥満、過度な飲酒、喫煙、運動不足など乱れた生活習慣を続けると、体力や呼吸機能が低下し、動悸や息切れを起こすことがあります。
ストレスや不安
 過度なストレスの蓄積や緊張、不安、パニック障害などは、自律神経のバランスを乱して血圧の上昇を促進し、動悸や息切れを起こすことがあります。
過度なストレスの蓄積や緊張、不安、パニック障害などは、自律神経のバランスを乱して血圧の上昇を促進し、動悸や息切れを起こすことがあります。
薬物や刺激物の摂取
アルコールやカフェイン、エナジードリンクの過剰摂取や喫煙などは、交感神経を活性化して興奮状態となり、動悸や息切れを起こすことがあります。
貧血
貧血になると体に供給する酸素量を維持するために、心臓はより多くの血液を循環させる必要が出てくるために、動悸や息切れを起こすことがあります。
高体温
発熱や熱中症、運動などによって体温が上昇すると、心拍数も上昇し、動悸や息切れを起こすことがあります。
動悸・息切れの症状
動悸は無意識に自分の心臓の拍動を感じ取れる状態で、息切れは意識的に呼吸をしないと息苦しさを感じる状態です。
動悸や息切れを引き起こす原因は様々であり、ほとんどは一過性のため、しばらく安静状態を保つと自然に治まります。しかし、動悸や息切れが長時間持続する場合や、頻発する場合には、何らかの病気の一症状として現れている可能性も考えられます。
以下に挙げたような症状が現れている場合は、病気が隠れている可能性がありますので、一度当院までご相談ください。
- 胸がドキドキする
- 胸痛が生じている
- 慢性的な倦怠感がある
- ちょっとした運動ですぐに息切れを起こす
- 意識的に呼吸をしないと息苦しくなる
- ゼーゼー音、ヒューヒューといった喘鳴が聞こえる
- 咳や痰が多く出る
- めまいやふらつきを起こすことがある
- 全身にむくみ症状がある
- 冷や汗が出る
- 失神することがある
動悸・息切れの検査
動悸・息切れの原因を調べる検査として、血液検査や心電図検査、胸部レントゲン検査、心エコー検査などがあります。病気が疑われる場合は、これらの複数の検査を行い、総合的に確定診断に繋げます。
血液検査
血液検査では、主にNT-proBNPや心筋トロポニンの数値を確認します。これらは、心臓に異常が生じていたり、心筋がダメージを受けていたりした際に上昇する特徴があるため、これらの数値が高い場合は、心不全、虚血性心疾患など心臓系の病気の疑いがあります。
心電図検査
心電図検査とは、身体の上から電極を取り付けて心拍の状態を確認する検査です。動悸や息切れとともに胸痛や脈の異常を伴っている場合は、狭心症や心筋梗塞、不整脈などの心臓疾患の疑いがあります。これらの病気を発症すると、心電図検査で特徴的な波形が検出されるため、確定診断に繋げることができます。
ホルター心電図検査
ホルター心電図検査とは、小型の機器を身体に取り付けて最大14日間の心拍の状態を記録することができる検査です。検診などで行う心電図検査は短時間で終了するため、検査中に動悸や息切れといった不整脈などの症状が現れないと見逃されてしまう恐れがあります。そのため、これら病気の疑いがある場合は、ホルター心電図検査を行って心拍の状態を長時間観察します。
胸部レントゲン検査
胸部レントゲン検査とは、心臓や肺、大動脈などの大きさや働きを確認することができる画像検査です。動悸や息切れを引き起こす肺うっ血や心肥大、心不全、胸水などの有無を確認することができます。
心エコー検査
心エコー検査とは、胸部や腹部に超音波を照射することで心臓の大きさや働き、心臓弁、血流などの状態を確認することができる検査です。動悸や息切れを引き起こす心不全や心臓弁膜症、心筋梗塞の有無を確認することができます。
動悸・息切れの治療
 動悸や息切れの原因は様々であり、原因によって症状の程度も異なります。多くの場合は深呼吸をしたりしばらく安静状態を保ったりすることで自然に治まります。ただし、いったん症状が治まったとしても、何らかの病気が隠れている場合もありますので、できるだけ早く当院までご相談ください。
動悸や息切れの原因は様々であり、原因によって症状の程度も異なります。多くの場合は深呼吸をしたりしばらく安静状態を保ったりすることで自然に治まります。ただし、いったん症状が治まったとしても、何らかの病気が隠れている場合もありますので、できるだけ早く当院までご相談ください。
動悸や息切れの治療も、症状の程度や原因疾患によって異なります。現れている症状が軽度で、心電図検査などでも特に異常が見つからない場合は、治療は行わずに経過観察に留める場合もありますが、一方、症状が強い場合や長時間継続している場合、頻発している場合などは重篤な心疾患などの疑いがあるため、早急に専門的な検査や治療を行う必要があります。
動悸・息切れのよくある質問
心臓がドキドキして息切れするときはどうすればいいですか?
まずは楽な姿勢を保ち、深呼吸をしてしばらく安静状態を維持してください。多くの場合は、その後自然に治まりますが、30分以上症状が継続する場合や、息苦しさが強まったり、気が遠くなるような症状が出てくる場合は医療機関に受診して下さい。いったん症状が治まったとしても、念の為医療機関を受診することを推奨しています。
また、アルコールやカフェインの過剰摂取をすると、交感神経が活性化して動悸や息切れを起こすことがあります。心当たりがある場合は、これらの摂取は控えるようにしましょう。
心不全の息切れはどのような時に起こりますか?
初期の段階では、階段の上り下りなどのちょっとした運動時に動悸や息切れを起こすようになります。しかし、病状が進行すると、平らな道の歩行時などでも動悸や息切れ、息苦しさを感じるようになります。
更に病状が進行すると、睡眠時などの横になった状態の時にも、動悸や息切れ、息苦しさ、咳などの症状が現れるようになります。
水分不足によって動悸は起こりますか?
激しい運動や炎天下で長時間活動すると、動悸や息切れを起こすことがあります。特に、激しい喉の渇きとともに動悸や息切れを起こした場合は、脱水症状の疑いがありますので注意が必要です。
動悸を放置するとどうなりますか?
動悸の原因は様々ですが、症状が強い場合や頻発する場合には何らかの病気が関与している可能性があります。そのため、いったん症状が治まったとしても、念の為医療機関を受診し、検査を行うことを推奨しています。
また、過度なストレスや不安、緊張など心因的要因も動悸を引き起こします。多くの場合は、しばらく安静状態を保つことで自然に治まりますが、過度なストレスの蓄積は、循環器系の病気を引き起こす恐れもあるため注意が必要です。実際に、日常的にストレスを抱えている人は、そうでない人と比べて心筋梗塞の発症率が1.5倍になると報告されています。
いずれにしても、動悸を起こした場合は、自己判断で放置せずにできるだけ早い段階で医療機関を受診し、原因を特定して治療を開始することが重要です。
異常がないのに動悸が出現するのはどうしてですか?
検査で身体的な異常が確認されないにも関わらず、動悸を起こしている場合は、ストレスや不安、緊張などの心因的要因や、アルコール、カフェインといった刺激物の過剰摂取などが原因として考えられます。これらは自律神経のバランスを乱し、交感神経が活性化することで動悸や息切れなどの症状を引き起こします。そのため、適度に休息する、趣味などリラックスした時間を積極的に取る、十分な睡眠時間を確保する、刺激物の過剰摂取を控えるなどの生活習慣を改善させることが、症状の緩和や予防にとって大切です。