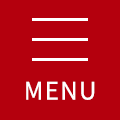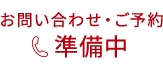生活習慣病とは
生活習慣病とは、食事習慣の乱れや運動不足、喫煙、過度な飲酒、過度なストレスの蓄積など、乱れた生活習慣を長期間継続することで引き起こされる病気の総称です。代表的な生活習慣病として、高血圧や脂質異常症、糖尿病などが挙げられます。
生活習慣病は、初期の段階では自覚症状に乏しく本人も気づかないうちに進行している場合が多く、次第に動脈硬化が進行し、脳卒中や狭心症、心筋梗塞、閉塞性動脈硬化症(ASO)など重篤な病気を引き起こすリスクも高まります。
生活習慣病の予防において最も大切なことは、生活習慣の改善です。当院では、薬物療法などの治療の他、効果的な生活習慣病の改善指導も行っております。ご希望がある方にはカウンセリングルームを設けておりますので、スタッフがじっくりとお話を聞き、マンツーマンでの継続的なコーチングを行うことも出来ます。
高血圧
 高血圧とは、血圧が慢性的に高い状態の病気です。血圧はその日の体調や気候、緊張、測定する場所などによって一時的に高まることがありますが、日にちや場所を変えて複数回測定しても高い数値が計測される場合は、高血圧の疑いがあります。具体的な高血圧の基準は、医療機関で測定した場合が140/90mmHg以上、ご自宅で測定した場合が135/85mmHg以上となります。ご自宅の方が低く設定されている理由は、ご自宅の方が医療機関よりもリラックスして測定できることで、血圧が低めに計測されることが多いためです。
高血圧とは、血圧が慢性的に高い状態の病気です。血圧はその日の体調や気候、緊張、測定する場所などによって一時的に高まることがありますが、日にちや場所を変えて複数回測定しても高い数値が計測される場合は、高血圧の疑いがあります。具体的な高血圧の基準は、医療機関で測定した場合が140/90mmHg以上、ご自宅で測定した場合が135/85mmHg以上となります。ご自宅の方が低く設定されている理由は、ご自宅の方が医療機関よりもリラックスして測定できることで、血圧が低めに計測されることが多いためです。
高血圧状態が長期間継続すると、全身の血管を損傷して動脈硬化を進行させ、脳卒中や心筋梗塞など重篤な病気を引き起こすリスクが高まります。そのため、高血圧(血圧が高い)を指摘された場合は、できるだけ早く薬物治療や生活習慣の改善を行うことが大切です。
高血圧の治療
高血圧の治療において最も大切なことは、乱れた生活習慣の改善となります。具体的には、食事療法や運動療法などを行って改善を図ります。食事では、脂質の多いメニューを避け、過度な飲酒は控えるようにしましょう。運動では、ウォーキングやジョギング、水泳などの習慣を取り入れてみましょう。その他、ストレスの多い生活をしている場合は、休息や趣味の時間を積極的に作り、上手にストレスを発散することも大切です。また、喫煙習慣がある場合は、禁煙しましょう。
これら生活習慣の改善を行っても十分な効果が得られなかった場合は、降圧剤などの薬物療法を検討します。ただし、これら薬の効果によって一時的に血圧の低下が見られたとしても、根本的な原因となっている生活習慣を改善しないと再発しますので、薬物療法と生活習慣の改善は同時並行で行うようにしましょう。
糖尿病
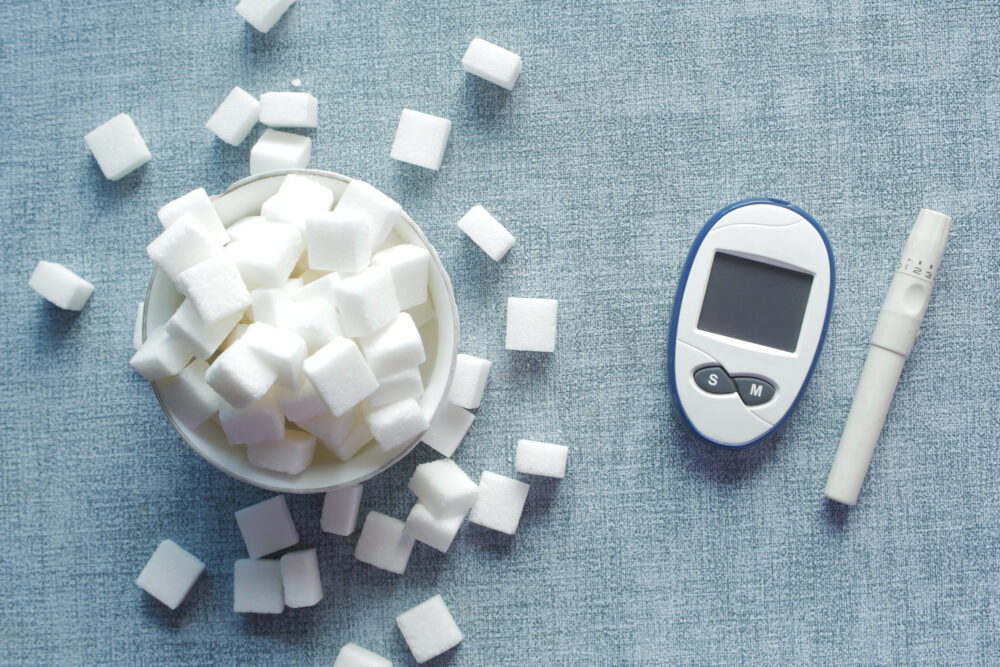 糖尿病とは、血液中の糖分が慢性的に過剰になった状態の病気で、1型糖尿病と2型糖尿病に大別されます。通常、食事から摂取した糖分を、インスリンによって脂肪やグリコーゲンなどのエネルギー源に変換し、肝臓や筋肉に貯蔵します。しかし、インスリンの分泌や機能が低下すると、糖分が血液中に溢れ、高血糖状態に陥り糖尿病を発症します。
糖尿病とは、血液中の糖分が慢性的に過剰になった状態の病気で、1型糖尿病と2型糖尿病に大別されます。通常、食事から摂取した糖分を、インスリンによって脂肪やグリコーゲンなどのエネルギー源に変換し、肝臓や筋肉に貯蔵します。しかし、インスリンの分泌や機能が低下すると、糖分が血液中に溢れ、高血糖状態に陥り糖尿病を発症します。
高血糖状態が続くと、全身の血管を損傷して動脈硬化を進行させ、様々な合併症を引き起こします。代表的な合併症として、脳梗塞や心筋梗塞などが挙げられます。また、高血糖状態は全身の毛細血管を破壊し、糖尿病網膜症による失明や下肢の細胞が壊死することによる下肢切断、人工透析を必要とする腎不全などの重篤な症状も引き起こすこともあります。
高血糖を指摘された場合には、糖尿病と診断される前に生活習慣の改善を行うことが重要です。
糖尿病の種類
1型糖尿病
1型糖尿病とは、膵臓のインスリン分泌機能が低下することで発症する糖尿病です。はっきりとした原因は明らかになってはいませんが、免疫機能の異常が関与していると考えられています。
1型糖尿病は若年層に多く見られる傾向があり、突然症状が現れる傾向にあります。症状として、喉の渇きや頻尿、急激な体重減少などが挙げられます。
主な治療は、インスリン注射になります。病状が進行して重篤な合併症を引き起こさないためにも、医師の指示に従って適切に血糖値をコントロールしていくことが重要です。
2型糖尿病
2型糖尿病は、日本に多く見られる糖尿病です。主な原因は、先天的な遺伝的要因が関与している場合と、生活習慣の乱れによる場合の2種類に分類されます。前者の場合は、遺伝的要因によって膵臓機能に異常が生じ、インスリンの分泌量が低下することが原因となります。後者の場合は、過食や肥満、脂質の多い食事、運動不足、過度な飲酒、喫煙、過度なストレスの蓄積などの生活習慣の乱れによって、インスリンの効果が低下することが原因となります。なお、2型糖尿病患者の多くは後者になります。
治療では、薬物療法やインスリン注射の他、生活習慣の改善を行います。これらを同時並行で行うことで、常に血糖値を適切な範囲に維持することが大切です。
糖尿病の3大合併症
糖尿病は様々な合併症を引き起こすことでも有名な生活習慣病です。中でも、糖尿病網膜症、糖尿病神経障害、糖尿病腎症は3大合併症と言われております。
また、糖尿病は動脈硬化を進行させることによって、心筋梗塞や脳梗塞など死の危険を伴う合併症をも引き起こします。これらは、初期の段階では自覚症状がほとんど現れずに進行するため注意が必要です。
糖尿病網膜症
糖尿病網膜症とは、高血糖の影響で網膜の毛細血管が閉塞し、網膜に酸素が行き届かなくなって網膜剥離を引き起こす合併症です。最終的には失明の危険性もあり、日本の失明原因の第2位を占めます。
糖尿病神経障害
糖尿病神経障害とは、高血糖の影響で手足の神経が障害を起こし、手足に痛みや痺れなどが現れる合併症です。症状が慢性化するほど進行すると足の細胞が壊死し、最終的には下肢切断が必要になるほど危険な状態となるため、注意が必要です。
糖尿病腎症
糖尿病腎症とは、高血糖の影響で腎臓の毛細血管が破壊される合併症です。病状が進行すると、腎臓機能が低下して腎不全を引き起こし、血液から老廃物を除去できなくなり人工透析治療が必要となります。
糖尿病の治療
糖尿病を根治させる治療法は、現時点で確立されておりません。そのため、糖尿病予備軍と診断されたら、早急に生活習慣を改善して糖尿病の発症を防ぐことが重要です。
糖尿病と診断されてしまった場合は、糖尿病によって引き起こされる合併症:心血管病 (脳梗塞、心筋梗塞、狭心症など)、網膜症、神経障害、腎症の予防が最重要となります。そのため血糖値を適切な数値 (HbA1c7.0%)を目標に治療しています。主な治療法は、食事療法や運動療法、薬物療法になります。
食事療法
糖尿病の大きな原因の一つに、過食や脂質の過剰摂取といった食事習慣の乱れがあります。そのため、食事療法では栄養バランスの取れた食事や、規則正しい食事時間の維持を重点的に行います。手引きとして、日本糖尿病学会が発行している「糖尿病食事療法のための食品交換表」「糖尿病性腎症の食品交換表」がお勧めですので、ぜひ参考にしてみてください。
食事療法は患者さま1人で行うことは難しいため、ご家族や医師などと連携しながら長期的に継続していくことが大切です。
運動療法
2型糖尿病は、主に運動不足によってインスリンが機能低下を起こすことが原因です。そのため、運動療法は2型糖尿病の改善に効果的です。運動は、ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動を長期間継続することが大切になります。その際、激しいメニューを組むと継続が難しくなるため、最初は軽い運動から始め、毎日着実に継続することを心がけましょう。当院でも改善指導を行っておりますので、お気軽にご相談ください。
薬物療法
食事療法や運動療法を行っても十分な改善効果が見られない場合には、薬物療法が検討されます。薬物療法の種類は多々あり、それぞれ治療機序や効果が異なります。薬物療法を選ぶ際に重要なのは、血糖値を下げるだけでは無く、糖尿病による合併症の発症をしっかり予防できることです。実は多々ある糖尿病の内服薬の中で、心血管病や腎症の予防効果を持っているモノは限られています。患者さまがお持ちの病気によって内服薬は選択されていきます。
ただし、薬物療法によって一時的に血糖値の低下が見られても、根本的な解決にはなりませんので、食事療法や運動療法も同時並行で行うことが重要となります。
なお、インスリン治療が必要と判断した場合には、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
糖尿病は心疾患にも影響するの?
糖尿病の合併症の中でも多く見られるのが、狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患です。糖尿病になると、虚血性心疾患のリスクは3倍になり、9人に1人が死亡しているという報告もあります。
また、糖尿病は心筋を損傷して心臓の働きを低下させ、糖尿病性心筋症を合併する可能性も高まります。重症化すると心不全に陥り、死亡することもあるため注意が必要です。
このように、糖尿病と心疾患には密接な関係があるため、糖尿病と診断された場合は、定期的に自身の心臓の状態を確認することが大切です。
脂質異常症(高脂血症)
 脂質異常症とは一般的に高脂血症と呼ばれている病気で、食事習慣の乱れなどにより、血液中の中性脂肪や悪玉コレステロールが過剰になった状態の生活習慣病です。これらが慢性的に過剰になると動脈硬化が起こり、様々な合併症を引き起こす恐れもあり、注意が必要です。
脂質異常症とは一般的に高脂血症と呼ばれている病気で、食事習慣の乱れなどにより、血液中の中性脂肪や悪玉コレステロールが過剰になった状態の生活習慣病です。これらが慢性的に過剰になると動脈硬化が起こり、様々な合併症を引き起こす恐れもあり、注意が必要です。
脂質異常症の診断基準
脂質異常症に該当するのは以下の診断基準のいずれかに該当する場合です。
| 脂質異常症の診断基準 | ||
| LDLコレステロール | 140 mg/dL 以上 | 高 LDLコレステロール血症 |
| 120~139 mg/dL | 境界域高LDLコレステロール血症 | |
| HDLコレステロール | 40 mg/dL 未満 | 低 HDLコレステロール血症 |
| トリグリセライド(中性脂肪) | 150 mg/dL 以上 | 高トリグリセライド血症(空腹時) |
| 175mg/dL以上 | 高トリグリセライド血症(随時) | |
| Non-HDLコレステロール | 170 mg/dL 以上 | 高 non-HDLコレステロール血症 |
| 150〜169 mg/dL | 境界域高 non-HDLコレステロール血症 | |
脂質異常症の治療
脂質異常症の原因のほとんどは食事習慣の乱れとなります。そのため、まずは食事習慣の改善が重要です。具体的には、炭水化物や脂質の摂取を避けることや、禁酒などを長期間継続するように努めましょう。
また、運動療法も脂質異常症の改善に効果的です。まずは無理のない範囲で、軽いウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動から始めてみましょう。
これらの食事療法や運動療法を行っても十分な改善効果が見られなかった場合は、薬物療法を検討します。一部の患者さまで生まれつき脂質の代謝異常をもっている方がいらっしゃいます。家族性脂質異常症(高脂血症)の患者さまは食事習慣や運動習慣と関係なく脂質異常症を発症しております。若年から発症していることが多く、早期の薬物治療を行う必要がありますので、気になる方はお気軽にご相談ください。