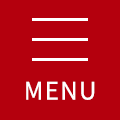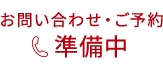心不全とは
 心不全とは、なんらかの原因によって心臓が全身に血液を上手に送り出せなくなり、動悸や息切れ、むくみ、疲労感、身体のだるさなどがみられる病気です。原因として不整脈、心筋梗塞、心臓弁膜症などの心疾患による心臓の動きの低下があげられますが、心臓の動きが正常であっても、加齢、高血圧、糖尿病、肥満などによっても生じてきます。
心不全とは、なんらかの原因によって心臓が全身に血液を上手に送り出せなくなり、動悸や息切れ、むくみ、疲労感、身体のだるさなどがみられる病気です。原因として不整脈、心筋梗塞、心臓弁膜症などの心疾患による心臓の動きの低下があげられますが、心臓の動きが正常であっても、加齢、高血圧、糖尿病、肥満などによっても生じてきます。
心不全には、心筋梗塞などで突然心臓の機能が低下し、発症する急性心不全とゆるやかに心臓の機能低下が進行する慢性心不全があります。
主な症状は、急性心不全の場合は激しい呼吸困難、横になれない強い息切れなどがあります。慢性心不全の場合は動悸や全身のむくみ、運動時の息切れ、倦怠感などが挙げられますが、心不全の治療が不十分ですと、慢性心不全が急性増悪し、急性心不全のように強い呼吸困難が突然生じる場合があります。
心不全パンデミックとは
心不全パンデミックとは、心不全の患者数増大によって医療従事者や病床数が不足している状態です。現在、日本における心不全の患者数は約120万人で、超高齢社会に伴って年々増加傾向にあります。このままでは全ての患者さまを網羅することができなくなる可能性が指摘されており、国策の一つとして問題の解決に向けて取り組んでいます。
問題解決の手段としては、心不全を起こさないための予防法を広く普及させることが大切になります。その上で、患者さまの症状の程度に合わせて、地域のクリニックや大学病院などの高度医療機関が相互に連携し、全ての患者さまに適切な医療サービスを提供できる体制を整えることが必要となります。
当院では、心不全の患者さまに対して最適な検査や治療を行っております。心不全に関して何かご不明な点やご質問などがございましたら、どうぞお気軽にご相談ください。
心不全の原因となる主な病気
虚血性心疾患
虚血性心疾患とは、動脈硬化などが原因で心臓に酸素や血液を供給する冠動脈が狭窄や閉塞を起こす病気です。心臓に栄養が行き届かなくなることで、心臓機能が低下し、最終的に冠動脈が完全に閉塞を起こすと、心筋が壊死して急性心不全を引き起こす恐れもあります。
虚血性心疾患の主な原因は動脈硬化となります。動脈硬化を引き起こす主な病気として、高血圧や肥満、脂質異常症、糖尿病などが挙げられます。
心臓弁膜症
心臓弁膜症とは、心臓を構成する4つの部屋 (右房、左房、右室、左室)を隔てている弁が適切に働かなくなる病気です。大動脈弁、僧帽弁、三尖弁、肺動脈弁の4つの弁にそれぞれ狭窄症と閉鎖不全症があります。弁の機能が低下すると、心臓が全身に十分な血液を送り出せなくなり、心臓の動きの低下、不整脈の出現、心不全などの問題が生じてきます。
考えられる原因としては、加齢や高血圧による動脈硬化、心筋梗塞、心筋症などがありますが、生まれつきの先天的な疾患も挙げられます。
心筋症
心筋症とは、何らかの原因によって心筋の機能に障害が起き、心臓機能の低下を引き起こす心疾患の総称です。虚血性心疾患による虚血性心筋症や他の病気が原因で心筋障害が生じる二次性心筋症、はっきりとした原因が分からずに発症する特発性心筋疾患があり、心臓機能が低下することで心不全を引き起こします。
心筋炎
心筋炎とは、ウイルス感染などが原因で心筋に炎症が起きる病気です。心筋が炎症を起こすと、心臓機能が低下して心不全を引き起こします。
先天性心疾患
心不全を引き起こす病気の中には、先天性のものもあります。代表的な病気として、生まれつき左右の心房を隔てる壁が穿孔を起こし、血液の逆流を招く心房中隔欠損症などが挙げられます。
従来は、先天性心疾患の治療法が確立していなかったため、患者さまが成人に達する前に死亡してしまうことが多く見られましたが、近年では医療技術の進歩により、多くの患者さまが先天性心疾患を抱えたまま成人に達することができるようになりました。なお、成人の先天性心疾患のことを、成人先天性心疾患(ACHD)と言います。
当院では、成人先天性心疾患(ACHD)の診療を積極的に行っています。お気軽にご相談ください。
不整脈
不整脈とは、心拍のリズムに異常が起きる病気です。不整脈には、脈が早くなる頻脈や脈が遅くなる徐脈、脈が飛ぶ期外収縮の3つのタイプがあります。
心臓が正常なリズムで拍動できなくなることにより、血液を拍出する効率が下がり、心不全を引き起こす恐れがあります。
心不全の症状
 心臓は、全身に血液を送り出す役割を担う臓器です。心不全を発症すると、全身に十分な血液を送り出せなくなり、様々な症状を引き起こします。
心臓は、全身に血液を送り出す役割を担う臓器です。心不全を発症すると、全身に十分な血液を送り出せなくなり、様々な症状を引き起こします。
主な心不全の症状は、動悸や息切れ、疲労感、倦怠感、むくみ、体重増加などが挙げられます。また、病状が進行すると、横になるだけで呼吸困難に陥ることから、座った状態でしか睡眠が取れない起坐呼吸などの症状を起こすこともあります。
特に、動悸や息切れ、むくみなどの症状は、比較的初期の段階で現れることが多いため、気になる症状が現れている場合は、できるだけ早めに医療機関を受診し、検査や治療を行うようにしましょう。
- 活動時の動悸・息切れ・息苦しさ
- 安静時の動悸
- 横になると呼吸が苦しくなる
- 足や身体のむくみ
- 短期間で体重が増加する
- 咳や痰が増える
など
心不全の検査
心不全の主な検査は、血液検査や心電図検査、胸部レントゲン検査、心エコー検査などになります。また、より高度な精密検査として、CT検査やMRI検査、運動負荷検査、心臓カテーテル検査、核医学検査などもあります。精密検査が必要な場合には、連携する高度医療機関をご紹介いたします。
血液検査
血液検査ではNT-proBNPの数値を測定します。NT-proBNPは心臓の負担具合を表し、心不全の重症度を評価する指標です。重症度が高いほど高い数値を示す特徴があります。
心電図検査
心電図検査とは、身体の上から電極を取り付けて心拍の状態を確認する検査です。検出される波形を見ることで、不整脈や心筋梗塞などの病気の有無や、心筋の異常の有無などを確認することができます。
胸部レントゲン検査
胸部レントゲン検査は、胸部を撮影することで心臓や大動脈、肺などの状態を確認することができる画像検査です。心不全になると、心臓機能が低下して心拡大や胸水、肺うっ血などの症状を引き起こしやすく、胸部レントゲン検査では、これらの異常を発見することが可能です。
心エコー検査
心エコー検査とは、身体に超音波を照射することで心臓の状態を確認することができる画像検査です。放射線を使用しないため、被ばくリスクはなく、痛みも伴わないため、患者さまの負担なく繰り返し行うことができます。
そして、なにより心臓の動きや血液の流れを視覚的に確認できるために、心不全の診断には最も重要な検査です。心臓弁膜症の有無、心不全の重症度などのあらゆる情報も確認することができます。
心不全の治療
 心不全は、様々な心臓の病気によって引き起こされるため、原因疾患に対して選択的な治療を行うと共に、正しい薬物治療を継続することが最も重要です。
心不全は、様々な心臓の病気によって引き起こされるため、原因疾患に対して選択的な治療を行うと共に、正しい薬物治療を継続することが最も重要です。
疾患毎の選択的治療としては、例えば原因疾患が狭心症や心筋梗塞の場合は、動脈硬化によって冠動脈が狭窄や閉塞を起こしているため、治療ではカテーテルを使用した経皮的冠動脈形成術 (PCI)や開胸手術による冠動脈バイパス手術が行われる必要があります。
その他、原因疾患が心臓弁膜症の場合は、異常を起こしている弁を修復するためのカテーテル治療や手術を行うことになります。これらの手術が必要と判断した場合は、当院が連携する高度医療機関をご紹介いたします。
薬物療法
薬物療法は心不全の悪化を防ぐだけでなく、心臓の機能自体を回復させる効果があります。そのため無症状の場合や症状が軽微な場合でも、心不全の病態によっては内服を行う必要があります。また一度心臓の機能が改善しても、内服を中断してしまうことで再度心臓の機能は低下してしまうことがあります。再度悪化した心臓の機能は回復しづらいことが知られていますので、内服は継続することが重要です。
主な心不全の治療薬は以下になります。
SGLT2阻害剤
当初、糖尿病の治療薬として開発された薬で、過剰な糖分を尿から排出する効果があります。しかしこの薬の効果は糖尿病だけに収まらず、糖尿病の無い方々の心臓の負担や腎臓の負担も下げることが分かりました。心不全と腎不全の予防効果もあるために、現在は糖尿病の有無に関係なく、心不全に対して第一選択の内服薬として推奨されています。
ARNI、ARB、ACE阻害剤、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 (MRA)
心不全の心臓は常にフルパワーで働いている状態です。この状態は、亢進した交感神経によって、心臓が鞭を打たれながら働いている状態です。この状態が続くと、心臓の機能は徐々に弱まり、心不全が増悪します。そのため交感神経を下げて、心臓を休ませ、心臓のパワーの回復を待つ必要があります。ARNIを始めとしたARBやACE阻害剤、MRAはレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系という交感神経の興奮機序をブロックし、心臓を休ませる薬です。主に降圧剤として使用されている薬ですが、高血圧の有無に関係なく、心臓の収縮する能力が低下した心不全に対して第一選択の内服薬として推奨されています。
βブロッカー
βブロッカーとはアドレナリン受容体という交感神経の興奮機序をブロックし、心臓を休ませる薬です。心臓を休ませ、心臓のパワーの回復を待つ薬ですが、βブロッカーに心臓収縮性を落とす効果があります。そのため、患者さまの状態を見ながら、徐々に薬の量を増やしていく必要があり、専門的な知識と経験を必要とする薬です。患者さま自身での調整は絶対に控えてください。心臓の収縮する能力が低下した心不全に対して第一選択の内服薬として推奨されています。
食事療法
塩分の過剰摂取は、身体に水が溜まって病状を悪化させる恐れがあります。また、肥満も心臓への負担を増大させて病状の悪化を招きます。そのため、食事療法では塩分や脂質などの過剰摂取を抑えるための改善指導を行います。
運動療法・心臓リハビリテーション
心臓リハビリテーションを始めとした運動療法は、心不全の患者さまに対して、退院後の再発を予防するための非常に強い効果が証明されています。特に有酸素運動や下肢筋力向上のための運動療法は、心肺機能のみならず、血管内皮機能も向上させます。しかし心不全を
発症した患者さまは、心臓機能が健常者と比べて低下していることから、過度な負荷にならないように適切な運動負荷量で運動療法を行っていく必要があります。
心臓リハビリテーションでは、専門の医師や看護師が患者さまの生活スタイルや症状の程度を考慮し、患者さま一人一人に対して適切な食事習慣の改善指導や運動療法をご提案いたします。
当院でも体制を整えていく予定ですので、開始する際はお知らせいたします。