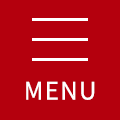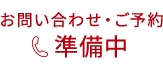心電図検査とは
 心電図検査は、身体の上から電極を取り付け、心臓の拍動の状態を観察することができる検査です。心臓の拍動は、洞結節で発生した電気信号が、心筋に規則正しく伝達されることで収縮・拡張を繰り返します。しかし、心臓に何らかの異常が起きると、このリズムが乱れ、心電図検査に特徴的な波形が検出されます。そのため、心電図検査で異常が指摘された場合は、何らかの心臓疾患を発症している可能性があり、注意が必要です。
心電図検査は、身体の上から電極を取り付け、心臓の拍動の状態を観察することができる検査です。心臓の拍動は、洞結節で発生した電気信号が、心筋に規則正しく伝達されることで収縮・拡張を繰り返します。しかし、心臓に何らかの異常が起きると、このリズムが乱れ、心電図検査に特徴的な波形が検出されます。そのため、心電図検査で異常が指摘された場合は、何らかの心臓疾患を発症している可能性があり、注意が必要です。
心電図検査で指摘されること
| 所見名 | 説明 | |
|---|---|---|
| 期外収縮 |
期外収縮とは、本来洞結節から発生する電気信号が何らかの原因によって、別の場所から発生してしまい、脈が飛ぶ症状です。 |
|
| 洞性不整脈 |
洞性不整脈とは、呼吸などの影響によって洞結節からの電気信号の発生が乱れ、脈拍が速くなったり遅くなったりする病気です。 |
※心電図検査で異常を指摘された際に考えられる主な原因です。これらの病気自体で問題になることは少ないですが、別の病気が隠れていることがありますので、医療機関に一度はご相談ください。 |
| 洞性徐脈 |
洞性徐脈とは、洞性不整脈のうち、脈拍が通常よりも遅くなった状態を言います。具体的には、心電図検査の波形は正常で、心臓からの電気刺激が50回/分未満の状態になると、洞性徐脈と診断されます。甲状腺機能低下症などがある場合に見られます。なお、日常的に運動習慣がある人にもよく見られます。 |
|
| 洞性頻脈 |
洞性頻脈とは、洞性不整脈のうち、脈拍が通常よりも早くなった状態を言います。具体的には、心電図検査の波形は正常で、心臓からの電気刺激が100回/分以上の状態になると、洞性頻脈と診断されます。 |
|
|
房室ブロック |
房室ブロックとは、心臓を動かすために心房から心室へ電気刺激を伝える際、電気刺激が遅延したり、途絶したりする病気です。 |
|
|
左室肥大 |
左室肥大とは、心臓の左心室の筋肉が厚くなり、左心室が硬化・肥大化を起こす病気です。左室肥大になると、心臓が拍動するのにより強い力が必要になるため、心電図検査で特徴的な波形が検出されます。主な原因は、高血圧や心臓弁膜症などの病気が挙げられます。 |
|
|
軸偏位 |
軸偏位とは、心臓を動かす電気刺激の伝達方向である電気軸が、左右に傾いている状態です。虚血性心疾患や心筋症、先天性心疾患の初期症状の場合があります。一度、医療機関を受診し、心エコーなどの検査が必要です。 |
|
|
高電位・低電位 |
高電位とは、心電図検査の際にQRS波という波形の振幅が大きい状態で、低電位とは、逆に波形の振幅が小さい状態を指します。高電位の場合は左室肥大を引き起こす病気が疑われ、低電位の場合は心臓タンポナーデや浮腫が強い場合に見られてきます。一度、医療機関を受診し、心エコーなどの検査が必要です。 |
|
|
平低T波・陰性T波・ST-T異常 |
平低T波とは、心電図検査の際にT波という波形が平坦になる状態で、陰性T波とは、波形が下向きになる状態です。また、ST-T異常とは、S波・T波の部分が上向きになったり、下向きになったりする状態です。 |
|
|
異所性P波 |
異所性P波とは、心電図検査でP波が通常とは異なる波形を示す状態です。ほとんどの場合は特に問題はありませんが、動悸や息切れなどの症状がある場合は、原因を特定することが大切です。 |
|
|
I度房室ブロック |
房室ブロックは、症状に応じてⅠ度〜Ⅲ度のタイプがあり、電気刺激の遅延が見られる状態をⅠ度房室ブロックと言います。狭心症や心臓サルコイドーシスなどの疑いがあります。 |
|
|
II度房室ブロック |
電気刺激が時々途絶する状態をⅡ度房室ブロックと言い、Ⅱ度にはウエンケバッハ型とモビッツ型Ⅱ型の2種類があります。Ⅱ度房室ブロックの場合には、心筋炎や狭心症などの疑いがあります。 |
|
|
2相性 |
2相性とは、心電図検査の際に通常は山形をしているT波が、山と谷が結合したような波形に変化する状態です。2相性T波は、主に心筋の血流に異常がある場合に見られます。 |
|
|
Q・QS型 |
心電図検査にはQ波、R波、S波があり、通常R波は上向き、Q波とS波は下向きの波形をしています。しかし、何らかの異常によってこれらの波形が乱れることがあり、Q波が大きくなる波形をQ型、R波が消失する波形をQS型といいます。これらの波形が検出された場合は、心筋症や心筋梗塞など心筋の病気を起こしている疑いがあります。 |
|
|
ST上昇 |
ST上昇とは、心電図検査のST部分が通常より高い位置を示している状態です。この波形が検出された場合は、心筋炎や心筋梗塞、ブルガーダ症候群などが疑われますが、若年層の健常者にも見られることがあるため、該当する場合は精密検査を行う必要があります。 |
|
|
ST低下 |
ST低下とは、心電図検査のST部分が通常より低い位置を示している状態です。この波形が検出された場合は、心筋の血流の悪化や心筋症などが疑われます。 |
|
|
T波増高 |
T波増高とは、心電図検査のT波が通常より高い山形の位置を示している状態です。この波形が検出された場合は、心肥大や血液中のカリウム過剰、心筋梗塞の初期状態などが疑われます。 |
|
|
T波平低 |
T波平低とは、通常では山形を示す心電図検査のT波が平らに示されている状態です。この波形が検出された場合は、心筋に過度な負担がかかっていたり、心筋障害を起こしていたりする可能性があります。ただし、女性の健常者にも見られることがあるため、該当する場合は精密検査を行う必要があります。 |
|
|
WPW症候群 |
WPW症候群とは、心房と心室の間に余分な伝導路が生まれ、不整脈を生じやすい状態の病気です。不整脈が生じていなければ無症状ですが、上室性頻拍や心房細動が生じると、動悸や息切れなどが生じます。不整脈が無ければ、経過観察になりますが、重篤な不整脈になる場合もあるため、慎重な観察が必要です。またパイロットなどの一部の職業に従事している方の場合、不整脈がなくても治療が必要となります。 |
|
|
陰性T波 |
陰性T波とは、通常では山形を示す心電図検査のT波が谷型に示されている状態です。この波形が検出された場合は、心筋に過度な負担がかかっていたり、心筋障害を起こしていたり、心筋症を発症している可能性があります。 |
|
|
右脚(うきゃく)ブロック |
右脚ブロックとは、心室にある2つの電気信号の伝導路 (右脚と左脚)の内、右脚の伝導が途絶え、左側から伝達されている状態です。主に、加齢などが原因で起こることが多く、特に問題はありませんが、心房中隔欠損症やファロー四徴症や肺高血圧症など右心室側の病気も疑われるため、精密検査を行うことを推奨しています。 |
|
|
右胸心 |
右胸心とは、本来は左側に位置している心臓が右側に位置する状態です。 |
|
|
右室肥大 |
右室肥大とは、心臓の右室の心筋の厚みが増したり、右室が肥大化を起こしたりしている状態です。主な原因は、肺高血圧や心臓弁膜症などが挙げられます。 |
|
|
右軸偏位 |
右軸偏位とは、電気信号が流れる電気軸が右側に偏っている状態です。通常、電気信号は、右上の右房から左下の左室に向かって流れますが、この流れが右側に偏っていると、右軸変異と診断されます。 |
|
|
右房負荷 |
右房負荷とは、心電図検査のP波の電位が通常よりも高い状態です。主に、先天性心疾患や弁膜症、肺高血圧症などによって、右心房に過剰な負荷がかかっている場合に現れる波形です。 |
|
|
完全房室ブロック |
完全房室ブロックとは、通常では右上の右房から左下の左室に向かって流れる電気信号が、途中で途絶し、心房と心室が個々に電気信号を発生させている状態の病気です。治療は、心臓ペースメーカーの埋め込み手術が検討されます。 |
|
|
左脚(さきゃく)ブロック |
左脚ブロックとは、心室にある2つの電気信号の伝導路 (右脚と左脚)の内、左脚の伝導が途絶え、右側から伝達されている状態です。原因は虚血性心疾患、心筋症およびペースメーカー植え込み後などがあげられ、精密検査を行って原因を特定することが重要です。左脚ブロックは、放置すると効率に心機能を低下させ、重篤な心不全となります。主な治療法としてCRT (心臓再同期療法)植え込み術があり、必要に応じて、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。 |
|
|
左室肥大 |
左室肥大とは、心臓の左室の心筋の厚みが増したり、左室が肥大化を起こしたりしている状態です。主な原因は、高血圧や心臓弁膜症などが挙げられます。 |
|
|
左軸偏位 |
左軸偏位とは、電気信号が流れる電気軸が左側に偏っている状態です。通常、電気信号は右上の右房から左下の左室に向かって流れますが、この流れが左側に偏っていると、左軸変異と診断されます。 |
|
|
左房負荷 |
左房負荷とは、心電図検査のP波の波形に変化が生じる状態です。主に、僧帽弁狭窄や心不全などによって、左心房に過剰な負荷がかかっている場合に現れる波形です。 |
|
|
上室性(じょうしつせい)期外収縮 |
上室性期外収縮とは、心臓の上部の心房から余分な電気信号が発生する状態です。主な原因は、過度なストレスの蓄積や興奮、緊張などが挙げられます。動悸や息切れ、脈拍が飛ぶなどの不整脈の症状が頻発している場合は、適切な治療を行うことが大切です。 |
|
|
上室性頻拍 |
上室性頻拍とは、心臓の上部である心房から過剰な電気信号が発生している状態です。主な症状は、突然現れる動悸や息切れなどが挙げられ、中には、失神を起こすこともあるため注意が必要です。動悸症状により、日常生活に支障が出る場合は、薬剤治療に加え、カテーテルアブレーション治療を行います。 |
|
|
心室性(しんしつせい)期外収縮 |
心室性期外収縮とは、通常であれば心臓の上部の心房から発生するはずの電気信号が、下部の心室から発生している状態です。通常よりも早いリズムで電気信号が発生するため、脈拍が飛ぶなどの不整脈の症状を引き起こします。 |
|
|
心室頻拍 |
心室頻拍とは、通常では心臓の上部の右心房から発生するはずの電気信号が、下部の心室から過剰に発生している状態です。放置すると、心不全などの重篤な症状を引き起こす恐れがあるため、早急に治療を行う必要があります。 |
|
|
心房細動 |
心房細動とは、心臓の上部である心房が過剰に興奮し、痙攣を起こしている状態の病気です。主な症状は、不整脈による動悸や息切れなどが挙げられ、左心房内で血栓が生じる恐れもあるため、早急に治療を行う必要があります。 |
|
|
時計回転、反時計回転 |
時計回転/反時計回転とは、心臓が正常な位置よりも時計回り(左方向)/反時計回り (右方向)にずれている状態です。 |
|
心電図異常からわかる病気
不整脈
心電図検査が異常な波形を示した際の最も多い原因は、不整脈による期外収縮となります。期外収縮の場合は、治療の必要はなく経過観察に留めることが多いですが、期外収縮の頻度が高いと、その後心房細動などの治療を要する不整脈に進行します。また房室ブロックなどの徐脈性の不整脈も見つけられます。
脈拍が早くなる、遅くなる、飛ぶなどの不整脈の症状は一過性の場合もありますが、症状が頻発している場合は、できるだけ早く医療機関を受診し、適切な検査や治療を行うことが重要です。
虚血性心疾患
 虚血性心疾患とは、心筋に異常が生じることで引き起こされる狭心症や心筋梗塞などの病気の総称です。虚血性心疾患を発症している患者さまが心電図検査を行うと、心筋虚血や心筋障害、Q波低下、R波低下などが検査結果に記載されることがありますが、注意すべきことは、心筋虚血の症状発作が生じている時でないと心電図異常が認められないということです。狭心症が疑われたときに、心電図が正常であっても、狭心症は否定できません。必要に応じて追加の検査が必要となります。心筋梗塞の罹患歴がある患者さまは、再発の恐れもあるため定期的な心電図検査が必要です。
虚血性心疾患とは、心筋に異常が生じることで引き起こされる狭心症や心筋梗塞などの病気の総称です。虚血性心疾患を発症している患者さまが心電図検査を行うと、心筋虚血や心筋障害、Q波低下、R波低下などが検査結果に記載されることがありますが、注意すべきことは、心筋虚血の症状発作が生じている時でないと心電図異常が認められないということです。狭心症が疑われたときに、心電図が正常であっても、狭心症は否定できません。必要に応じて追加の検査が必要となります。心筋梗塞の罹患歴がある患者さまは、再発の恐れもあるため定期的な心電図検査が必要です。
また、過去に前胸部痛を起こしたことがある場合や、糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病に罹患している場合、長期間の喫煙習慣がある場合なども、虚血性心疾患を発症・進行している恐れがあります。
狭心症とは
狭心症とは虚血性心疾患の一種で、主に動脈硬化などが原因で、心臓の冠動脈が狭窄を起こしている状態の病気です。放置すると、冠動脈が完全に閉塞を起こし、心筋が壊死する心筋梗塞へと進行する恐れがあるため注意が必要です。
狭心症は、症状によって安定性狭心症、冠攣縮性狭心症、不安定狭心症の3つに分類されます。
心筋梗塞とは
心筋梗塞とは虚血性心疾患の一種で、主に動脈硬化などが原因で、心臓の冠動脈が閉塞を起こしている状態の病気です。一般的に40〜50代に多く見られる傾向があり、心筋に血液が供給されなくなることにより、心筋が壊死します。なお、一度壊死した心筋は、二度と再生しません。
また、心筋が壊死することで心臓のポンプ機能が低下し、全身に適切な量の血液を送り出せなくなり、心不全や不整脈、心臓弁膜症などの重篤な病気を合併する恐れがあります。中には突然死を招く恐れもあり、注意が必要です。
心筋症
心筋症とは、何らかの原因によって心筋の機能が低下している病気です。一部の心筋症では特徴的な心電図変化を示すことがあります。そのため心電図をきっかけに精査が進み、心筋症が診断される場合があります。
心室内伝導障害
心室内伝導障害とは、心室の電気回路が一部障害を受けており、伝導が遅れている状態です。不完全右脚ブロック、左脚前肢ブロック、左脚後枝ブロック、完全右脚ブロック、完全左脚ブロック等があります。
不完全右脚ブロックや完全右脚ブロックは、成人の場合には問題になるケースは少ないですが、心房中隔欠損症などの先天性の心疾患が偶発的に見つけられる可能性があるため、精密検査を行う必要があります。一方、完全左脚ブロックは何らかの心臓の異常が生じている可能性が非常に高く、精査が必ず必要です。
その他
心電図によって左室肥大または心肥大が分かります。主に、高血圧による心筋の肥大を表すために用いられることがあります。肥大の程度は、心エコー検査で確認しますが、将来的に心不全のリスクにつながりやすいため、高血圧を治療し、将来の心疾患を予防することが重要です。
心電図異常を指摘され「要精査」となった方へ
 検診などの心電図検査で異常を指摘された場合は、心電図検査の再検査や心エコー検査を実施します。心電図検査は、時系列で変化の有無を確認することが大切であるため、前回と波形に変化が現れていないかどうかを重点的に確認します。変化が見られた場合は、何らかの病気が隠れている可能性があるため、精密検査によって更に詳しい状態を確認する必要があります。
検診などの心電図検査で異常を指摘された場合は、心電図検査の再検査や心エコー検査を実施します。心電図検査は、時系列で変化の有無を確認することが大切であるため、前回と波形に変化が現れていないかどうかを重点的に確認します。変化が見られた場合は、何らかの病気が隠れている可能性があるため、精密検査によって更に詳しい状態を確認する必要があります。
また不整脈の疑いがある場合は、ホルター心電図検査を行い、心拍の状態を長時間観察します。また、心不全の程度を評価するために、血液検査(NT-proBNP)も合わせて実施します。
その他、心電図検査の再検査や心エコー検査によって虚血性心疾患や心筋症の疑いがある場合は、胸部CT検査やMRI検査を実施します。
なお、これらの精密検査が必要と判断した場合は、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
非特異的心電図異常とは
非特異的心電図異常とは、心電図検査で異常を指摘されたにも関わらず、精密検査を行っても、心臓には器質的異常が見当たらない状態を指します。
非特異的心電図異常は、60代以上の女性に多く見られる傾向があります。原因は明らかになってはいませんが、心筋の電気信号伝達が部分的に遅延するためと考えられています。ただし、次の検診の際も同様の検査結果となった場合は、初期の心疾患を発症している可能性もあるため、精密検査などで詳しく状態を確認する必要があります。
心電図検査のよくある質問
心電図検査に異常があると指摘されましたが、不整脈ですか?
心電図検査で異常を指摘された場合、最も考えられる原因は不整脈となります。しかし、一過性の不整脈は、健常者にもしばしば見られるため、医師が再検査や精密検査を指示しない限り、特に心配する必要はありません。
ただし、その後も動悸や息切れ、めまいなどの自覚症状が現れた場合は、できるだけ早い段階で当院までご相談ください。
危険な不整脈はありますか?
最も危険と言われる不整脈は心室細動になります。心室細動とは、心室が痙攣を起こしている状態で、命の危険を伴うこともある重篤な不整脈となります。
一般的に、重度の心不全や心筋梗塞、心筋症などに罹患している人が引き起こされやすい傾向があるため、注意が必要です。
その他に心室頻拍、心房細動や高度房室ブロックは専門的な治療が必要な不整脈になります。
心電図検査に異常があると指摘されましたが、自覚症状がなければ問題ないですか?
自覚症状がなく、心臓に異常が見つからなくても、心電図検査で異常を指摘されることがあります。ただし、多くの心疾患は、初期の段階では自覚症状に乏しいことが多いため、医師の指示に従い、必要であれは追加で精密検査を行うようにしましょう。
ストレスによって不整脈になりますか?
過度にストレスを蓄積すると、自律神経のうち交感神経が有意となって不整脈を引き起こすことがあります。実際、健常者や若年者でも心的要因によって、一時的に不整脈を起こすことがあります。
心臓に器質的異常が見当たらないにも関わらず、不整脈を引き起こす原因としては、ストレスの他に、過度な飲酒やカフェインの過剰摂取、睡眠不足、過労、喫煙なども挙げられます。
不整脈を感じた時の対処方法はありますか?
不整脈を起こした場合は、まずは深呼吸をして安静状態を保つことが大切です。安静状態になることで、自律神経のうち副交感神経が有意となり、動悸や息切れ、めまいなどの不整脈の症状を緩和させる効果が期待できます。
不整脈の際におこなってはいけないことはありますか?
不整脈の中には、健常者が一時的に起こす問題のないものもあります。しかし、中には初期の心疾患の可能性も否定できないため、自己判断で放置すると、病状を悪化させる恐れがあります。
また、飲酒時や運動時などに動悸や息切れ、意識が遠のくなどの症状が頻発する場合は、飲酒や運動を控えるようにしましょう。その他、ストレスや睡眠不足、過労などが不整脈を引き起こすこともあるため、心当たりがある場合は無理に活動せず、意識的に休息を取るなどして、心身を休めるよう心がけましょう。
いずれにせよ、気になる症状が現れている場合は自己判断せずに、医療機関を受診して医師の指示に従うことが大切です。