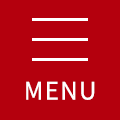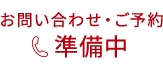心筋症とは
 心筋症とは、何らかの原因によって心筋の機能に障害が起き、心臓機能の低下を引き起こす心疾患の総称です。
心筋症とは、何らかの原因によって心筋の機能に障害が起き、心臓機能の低下を引き起こす心疾患の総称です。
狭心症や心筋梗塞など虚血性心疾患による心筋症を虚血性心筋症と言い、一方ではっきりとした原因が分からずに発症する心筋症を特発性心筋疾患と言います。なお、特発性心筋疾患は、心筋が拡大する拡張型心筋症、心筋が硬化する拘束型心筋症、心筋の厚みが増す肥大型心筋症に分類されます。更に、肥大型心筋症は、心室の出口が狭窄を起こす閉塞性肥大型心筋症と、狭窄を起こさない非閉塞性肥大型心筋症に分類されます。また心筋にアミロイドという異常蛋白が沈着し心筋障害が生じているアミロイドーシス心筋症、自己免疫により心筋障害が生じている心臓サルコイドーシス、遺伝子異常によってαガラクトシダーゼ活性が低下し、細胞内の糖脂質代謝が低下することで心筋障害が生じているファブリー病などは、原因が明らかなものとして二次性心筋症と呼ぶこともあります。
心筋症の原因
虚血性心筋症の主な原因は、動脈硬化などによる冠動脈の狭窄や閉塞です。一方、特発性心筋症の発症原因は、明確にはなってはいませんが、近年の研究によって徐々に解明されつつあります。
心筋症の原因となる主な病気
心筋炎
心筋炎とは、ウイルス感染などが原因で心筋が炎症を起こす病気で、心臓の風邪のような病気です。急性型や慢性型、劇症型、拡張型心筋症類似型など様々なタイプがあり、症状が現れる期間も、急性型の場合は数時間〜2週間程度ですが、慢性型の場合は長期間に及ぶことがあります。また、症状の程度も、根治が期待できるものから命の危険を伴う重篤なものまで様々です。
高血圧性心筋症
高血圧性心筋症とは、長期にわたる高血圧が続くことで、心臓の筋肉が肥大していく病気です。当初は心臓の筋肉の拡張能が低下していきますが、その後収縮能が失われていき、心臓のポンプ機能が低下して、心不全の発症リスクを高めます。
高血圧は心不全以外にも様々な病気のリスク要因となります。そのため、食事ではできるだけ塩分を控えるなど、日頃から生活習慣を整えることが大切です。
拡張型心筋症
拡張型心筋症とは、心筋が薄く拡張して心臓機能が低下する病気です。主な原因は高血圧、糖尿病、過度な飲酒などがありますが、原因が分からない特発性拡張型心筋症もあります。
症状の程度は様々であり、無症状のものもあれば、動けなくなるほど重篤化するもの、突然死を引き起こすものなどもあります。
肥大型心筋症
肥大型心筋症とは、原因不明に心筋の厚みが増大し、心臓の拡張する能力が低くなる病気です。進行すると心臓の収縮する能力も下がってきます。また心室の出口部分の心筋の厚みが増して狭窄を起こしている場合、閉塞性肥大型心筋症といいます。閉塞性肥大型心筋症は心室の出口部分の狭窄により血液が上手に流れない状態なので、狭窄を解除する特別な治療が必要となります。場合があります。このような心臓機能が低下する病気です。遺伝的要因の関与が考えられていますが、中には遺伝しない場合もあります。
症状の程度は様々であり、無症状のものもあれば、動けなくなるほど重篤化するものもあります。肥大型心筋症は不整脈のリスクが高いです。心筋が極端に厚い場合や閉塞性肥大型心筋症などは心室頻拍などの突然死を引き起こす不整脈のリスクがあり、若年層の突然死の原因の一つとも言われています。
心臓サルコイドーシス
サルコイドーシスとは、臓器に肉芽腫が発生する免疫性の病気です。自己免疫によって引き起こされる炎症によってさまざまな臓器に障害が生じます。心臓に炎症が発生した場合を心臓サルコイドーシスと言い、心臓にだけ炎症の発生が限定されている場合を心臓限局性サルコイドーシスと言います。
世界でも日本における心臓サルコイドーシスの発症率は高く、男性よりも女性に多く見られる傾向があります。また、男性の場合は20代に多く見られ、女性の場合は中高年に多く見られる特徴があります。
初期は無症状ですが、未治療のまま経過すると、徐脈性不整脈や頻拍性不整脈を合併します。心臓の機能も低下していくため、動悸や息切れ、失神、稀に心停止や突然死を引き起こすこともあるため注意が必要です。多くは健診などでの心電図異常や胸部レントゲンの異常、不整脈の精査などで偶発的に見つかることが多いです。しかし診断は難しく、専門医でも見落としてしまうことがある難しい病気です。
たこつぼ型心筋症
たこつぼ心筋症とは、主に全身に血液を送り出す役割を担う心臓の左心室の心筋が突然異常を起こし、様々な症状を引き起こす心筋症です。女性の高齢者に多く見られ、主な原因はストレスと考えられていますが、未だはっきり分かっていません。
主な症状は、動悸や息切れ、胸痛、胸の圧迫感、吐き気、失神などが挙げられ、これらが突然発症します。心筋梗塞と類似した症状であるため、診断では心筋梗塞との鑑別が必要となります。多くは自然軽快し、正常な心臓に戻っていきますが、発症中は不整脈のリスクがあるため、入院での治療となります。
アミロイド心筋症
アミロイド心筋症とは、アミロイドという異常蛋白がさまざまな臓器に沈着し、臓器の障害を引き起こす病気です。心臓に沈着すると心臓の拡張する能力が下がってきます。さらに進行すると収縮する能力も下がり、心不全を発症します。心臓の筋肉にアミロイドが沈着するため、心筋は厚くなり、肥大型心筋症と誤診されることがあります。アミロイドにはいくつかの種類がありますが、心臓にはALアミロイドーシスとATTRアミロイドーシスが関与していることがほとんどです。ALアミロイドーシスは免疫グロブリン軽鎖由来のアミロイドであり、主に免疫系の異常によって生成されます。非遺伝性で、血液系の腫瘍と関連しています。一方ATTRアミロイドーシスはトランスサイレチン(TTR)タンパク質由来のアミロイドが原因で発症するアミロイドーシスです。遺伝性のATTRvと非遺伝性のATTRwtがあります。ATTRvは遺伝的な変異によって引き起こされ、ATTRwtは高齢によって発症することがあります。初期は無症状ですが、未治療のまま経過すると、徐脈性不整脈や頻拍性不整脈を合併します。心臓の機能も低下していくため、動悸や息切れ、失神を引き起こすこともあるため注意が必要です。多くは健診などでの心電図異常や不整脈の精査などで偶発的に見つかることが多いです。また手根管症候群や脊柱管狭窄症と多く合併していることから手足のしびれを精査している中で見つかることがあります。しかし診断は難しく、専門医でも見落としてしまうことがある難しい病気です。ALアミロイドーシスは血液腫瘍に対する抗がん剤治療が必要となります。ATTRアミロイドーシスは内服薬による治療によって進行を抑制できるという報告がなされ、日本でも内服薬での治療が開始となっています。
心筋症の症状
心筋症は初期の段階では自覚症状に乏しいことが多く、健診などの心電図検査や胸部レントゲン検査、心エコー検査などで偶然発見されることが多く見られます。また、気づかずに病状が進行すると、心不全を引き起こして息切れや足のむくみなどの症状が現れるようになります。その他、不整脈を合併すると動悸や失神などを起こすこともあります。
心筋症の検査
血液検査
 血液検査では、主に心筋トロポニンとNT-proBNPを測定します。
血液検査では、主に心筋トロポニンとNT-proBNPを測定します。
心筋トロポニンは心筋の状態を評価する指標で、心筋梗塞などで心筋が壊死すると、血液中の心筋トロポニン含有量が増加します。
NT-proBNPは心臓の負担具合を表しており、心不全の重症度を評価する指標です。重症度が高いほど高い数値を示す特徴があります。
なお、心筋トロポニンは迅速キットを使用して行うため、短時間で判定結果を知ることができます。ただし、発症初期の段階では心筋の壊死が確認されず、偽陰性判定が出てしまうこともあります。
心電図検査
心電図検査とは、身体の上に電極を取り付けて心拍の状態を確認する検査です。ベッドに横になるだけで、比較的短時間で患者さまに痛みを与えることなく行うことができます。
急性心筋梗塞を発症している場合は、心電図検査に特徴的な異常が検知されるため、確定診断に繋げることができます。
心エコー検査
心エコー検査とは、身体に超音波を照射することで心臓の状態を確認することができる画像検査です。放射線を使用しないため、被ばくリスクはなく、痛みも伴わないため、患者さまの負担なく繰り返し行うことができます。
そしてなにより心臓の動きや血液の流れを視覚的に確認できるために、心筋症の診断には最も重要な検査です。心臓弁膜症の有無、心不全の重症度などのあらゆる情報も確認することができます。
心臓MRI検査
心臓MRI検査とは、電磁波をつかい心臓の形や動きを調べる画像検査です。放射線を使用しないため、被ばくリスクはなく、痛みも伴わないため、患者さまの負担なく行うことができます。3Dでの良質な画像を取得できるために、心臓の機能を高精度に評価できます。また造影剤を用いることで心臓の筋肉の性状も調べることが出来るために、心筋症の正確な診断のためには重要な検査です。
心臓カテーテル検査
心臓カテーテル検査とは、体内にカテーテルを挿入して心臓の冠動脈まで誘導し、冠動脈に造影剤を注入し、冠動脈の状態を確認する検査です。冠動脈の狭窄や閉塞の有無や場所、症状の程度などを確認することができます。また心臓の筋肉に異常な沈着成分がないかどうかを調べるために、心臓の筋肉の一部を採取して、顕微鏡で調べる心筋生検という検査を行う場合もあります。
なお、心臓カテーテル検査を行うには入院が必要となります。入院が必要な場合には、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
心筋症の治療
薬物療法
心筋症の治療は薬物療法が中心となります。無症状の場合は、薬物療法を行わずに経過を見ることもありますが、治療薬は心筋症の悪化を防ぐだけでなく、心臓の機能自体を回復させる効果があります。そのため無症状の場合や症状が軽微な場合でも、心筋症の病態によっては内服を行っていただきます。また一度心臓の機能が改善しても、内服を中断してしまうことで再度心臓の機能は低下してしまうことがあります。再度悪化した心臓の機能は回復しづらいことが知られていますので、内服は継続することが重要です。
主な心筋症の治療薬は以下になります。
SGLT2阻害剤
当初、糖尿病の治療薬として開発された薬で、過剰な糖分を尿から排出する効果があります。しかしこの薬の効果は糖尿病だけに収まらず、糖尿病の無い方々の心臓の負担や腎臓の負担も下げることが分かりました。心不全と腎不全の予防効果もあるために、現在は糖尿病の有無に関係なく、心筋症に対して第一選択の内服薬として推奨されています。
ARNI、ARB、ACE阻害剤、ミネラルコルチコイド受容体拮抗薬 (MRA)
心臓は心筋症という病気にかかりながらも、血液を全身に送り続けなければいけません。そのため心臓を常にフルパワーで働かせる必要があるため、体は交感神経を亢進させ、心臓に鞭を打って働かせます。この状態が続くと、心臓の機能は徐々に弱まってきます。そのため交感神経を下げて、心臓を休ませ、心臓のパワーの回復を待つ必要があります。ARNIを始めとしたARBやACE阻害剤、MRAはレニン・アンジオテンシン・アルドステロン系という交感神経の興奮機序をブロックし、心臓を休ませる薬です。主に降圧剤として使用されている薬ですが、高血圧の有無に関係なく、心臓の収縮する能力が低下した心筋症に対して第一選択の内服薬として推奨されています。
βブロッカー
βブロッカーとはアドレナリン受容体という交感神経の興奮機序をブロックし、心臓を休ませる薬です。心臓を休ませ、心臓のパワーの回復を待つ薬ですが、βブロッカーに心臓収縮性を落とす効果があります。そのため、患者さまの状態を見ながら、徐々に薬の量を増やしていく必要があり、専門的な知識と経験を必要とする薬です。患者さま自身での調整は絶対に控えてください。心臓の収縮する能力が低下した心筋症に対して第一選択の内服薬として推奨されています。
手術療法
病状が進行している場合や薬物療法では十分な改善効果が見られない場合は、手術療法を検討します。主な手術療法は、CRT埋め込み術や心臓移植などが検討される場合もあります。なお、手術が必要と判断した場合には、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。