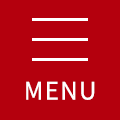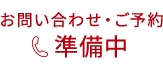循環器内科とは
 循環器内科は、心臓や全身の血管を専門的に診療する診療科です。代表的な病気としては、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった成人習慣病から心不全、虚血性心疾患、狭心症、心筋梗塞、心臓弁膜症、不整脈、先天性心疾患といった心臓病や大動脈瘤、大動脈解離といった血管病などがあります。
循環器内科は、心臓や全身の血管を専門的に診療する診療科です。代表的な病気としては、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった成人習慣病から心不全、虚血性心疾患、狭心症、心筋梗塞、心臓弁膜症、不整脈、先天性心疾患といった心臓病や大動脈瘤、大動脈解離といった血管病などがあります。
循環器内科で扱う病気の中には命の危険を伴う重篤なものもありますが、多くは早期発見・早期治療を行うことで改善もしくは予防することが可能です。気になる症状がございましたら、お気軽に当院までご相談ください。
循環器内科でよくある症状
- 胸痛(前胸部が締め付けられる痛み、重しが乗ったような苦しさ)
- 胸や心臓に違和感がある
- 左腕から肩にかけて痛い
- 背中が痛い
- 息苦しい・胸が苦しい
- 昔に比べて息切れを感じる
- 階段を上ると息切れがする
- 朝・夜中に咳が出る
- 息が苦しくて横になれない
- むくみ
- 体重増加
- 動悸
- 脈が飛ぶ
- 脈が遅くなる(徐脈)
- 脈が速くなる(頻脈)
- 昼間の眠気
- お腹のコブが拍動している
- 胸部レントゲン検査で異常を指摘された
- 心電図検査で異常を指摘された
など
循環器内科でよくある病気
- 心不全
- 心臓弁膜症
- 狭心症
- 心筋梗塞
- 心筋症
- 不整脈
- 成人先天性心疾患(ACHD)
- 肺高血圧症
- 肺血栓塞栓症
- 大動脈疾患(大動脈解離、大動脈瘤、深部静脈血栓症、閉塞性動脈硬化症)
- 高血圧
- 糖尿病
- 脂質異常症
- 睡眠時無呼吸症候群
など
心不全
心不全とは、心臓が全身に血液を上手に送り出せなくなり、動悸や息切れ、むくみ、疲労感、身体のだるさなどがみられる病気です。原因として不整脈、心筋梗塞、心臓弁膜症などの心疾患による心臓の動きの低下があげられますが、心臓の動きが正常であっても、加齢、高血圧、糖尿病、肥満などによっても生じてきます。
心不全には急性心不全と慢性心不全があります。急性心不全は、心筋梗塞などの心臓病を発症することで突然心臓の機能が低下し、発症します。一方で慢性心不全はゆるやかに心臓の機能低下が進行していきます。
主な症状は、急性心不全の場合は激しい呼吸困難、横になれない程の強い息切れがあります。慢性心不全の場合は、動悸や全身のむくみ、運動時の息切れ、倦怠感などが挙げられますが、治療が不十分ですと、急性増悪し、急性心不全のような強い呼吸困難が生じます。
緊急入院が必要となる場合がありますので、歩行が困難になるほどの強い息切れを起こしている場合は、できるだけ早めに当院までご相談ください。
現在、65歳以上の方の3人に1人が心不全を発症していると言われています。また症状はないけれど、心臓の動きが低下し始めている『心不全の予備軍』の方々はさらに多くいらっしゃると言われています。心不全は早期治療がとても大切です。動悸や息切れ、むくみなどが気になる方はお気軽に当院までご相談ください。
心臓弁膜症
心臓弁膜症とは、心臓を構成する4つの部屋 (右房、左房、右室、左室)を隔てている弁が適切に働かなくなる病気です。大動脈弁、僧帽弁、三尖弁、肺動脈弁の4つの弁にそれぞれ狭窄症と閉鎖不全症があります。弁の機能が低下すると、心臓が全身に十分な血液を送り出せなくなり、心臓の動きの低下、不整脈の出現、心不全などの問題が生じてきます。
考えられる原因としては、加齢や高血圧による動脈硬化、心筋梗塞、心筋症などがありますが、生まれつきの先天的な疾患も挙げられます。
主な症状は、動悸や息切れ、全身のむくみ、疲労感などです。
初期の段階では、薬物療法によって症状を改善させることができますが、弁膜症の種類や重症度によっては手術療法が必要となります。手術療法と聞くと怖い気持ちになるかと思いますが、現在ではカテーテル治療という胸を開ける必要のない低侵襲な治療法や小切開低侵襲心臓手術 (MICS)という小さい傷で行える手術があります。これらの治療は実施できる医療機関が限られてきますので、当院では患者さまに最適な治療法を提案させていただき、その治療法を提供できる高度医療機関に責任を持ってご紹介いたします。
心臓弁膜症は薬物治療を選択するか、手術療法を選択するかの判断はもちろん、手術療法を行うタイミングの判断も非常に難しいご病気です。専門家に一度相談してみたいという方は、当院までお気軽にお越しください。
狭心症
狭心症とは、動脈硬化によって心臓に酸素を運搬する冠動脈の血流が阻害され、心臓の筋肉が酸素不足に陥って様々な症状を引き起こす病気です。主な症状としては、動悸や息切れ、運動時の胸痛、左肩痛の他、吐き気や歯痛を伴うみぞおち痛を起こすこともあります。症状は比較的短時間で、安静にすると数分 (2〜3分程度)で治まってきます。
主な原因は高血圧、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病、喫煙などによる動脈硬化です。安静にすると症状が治まってくる段階は狭心症といいますが、安静にしても症状が治まらず、心臓の筋肉が壊れてしまう状態になると心筋梗塞となります。心筋梗塞となると、命の危険を伴うため高度医療機関に緊急入院していただき、治療を行う必要が出てきます。
そのため、狭心症の段階で治療を行うことが重要です。狭心症を疑う症状が現れた際には、できるだけ早く当院にまでご相談ください。
心筋梗塞
 心筋梗塞とは、動脈硬化によって冠動脈が閉塞もしくは高度に狭窄を起こし、心臓の筋肉 (心筋)への血流が阻害されて心筋が壊死を起こす病気です。主な症状は、30分以上に及ぶ激しい胸痛や嘔吐、呼吸困難、冷汗などがあります。高血圧、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病、喫煙者や高齢の患者さまに多く見られる傾向があり、発症すると命の危険を伴うため高度医療機関に緊急入院していただき治療する必要が出てきます。
心筋梗塞とは、動脈硬化によって冠動脈が閉塞もしくは高度に狭窄を起こし、心臓の筋肉 (心筋)への血流が阻害されて心筋が壊死を起こす病気です。主な症状は、30分以上に及ぶ激しい胸痛や嘔吐、呼吸困難、冷汗などがあります。高血圧、脂質異常症(高脂血症)、糖尿病、喫煙者や高齢の患者さまに多く見られる傾向があり、発症すると命の危険を伴うため高度医療機関に緊急入院していただき治療する必要が出てきます。
心筋症
心筋症とは、何らかの原因によって心筋の機能に障害が起きる心疾患の総称です。
狭心症や心筋梗塞など虚血性心疾患による心筋症を虚血性心筋症と言い、一方ではっきりとした原因が分からずに発症する心筋症を特発性心筋疾患と言います。なお、特発性心筋疾患は、心筋が拡大する拡張型心筋症、心筋が硬化する拘束型心筋症、心筋の厚みが増す肥大型心筋症に分類されます。また心筋にアミロイドという異常蛋白が沈着し心筋障害が生じているアミロイドーシス心筋症、自己免疫により心筋障害が生じている心臓サルコイドーシス、遺伝子異常によってαガラクトシダーゼ活性が低下し、細胞内の糖脂質代謝が低下することで心筋障害が生じているファブリー病などは、心筋障害の原因が明らかなものとして二次性心筋症と呼ばれています。
心筋症の初期の段階では、自覚症状が乏しく、本人も気づかないことが多いですが、病状が進行すると心不全を引き起こし、息切れや足のむくみなどの症状が現れるようになります。また、不整脈に陥った場合には、動悸や失神を起こすこともあります。
そのため、定期的に心電図検査や胸部レントゲン検査、心エコー検査などを実施して、自身の心臓の状態を確認しておくことが大切です。さらに、二次性心筋症はそのタイプによっては特殊な治療法が必要になる場合があります。その際には高度医療機関と連携を取りながら診断、治療を進めさせていただきます。
不整脈
不整脈とは、何らかの原因によって心臓の脈 (拍動リズム)が乱れる病気です。主な原因としては虚血性心疾患、心臓弁膜症、心筋症などの心臓病の他に、甲状腺疾患、睡眠時無呼吸症候群などの病気、疲労や過度なストレスの蓄積、脱水症状などによっても生じます。
不整脈の症状は、心臓の拍動が早くなる、拍動が遅くなる、拍動が一定時間飛ぶなど様々ですが、これらは自覚症状がない場合もあります。また、不整脈は放置すると心臓の中に血の塊が出来てしまい、脳梗塞を引き起こす恐れがあります。気になる症状がある場合はもちろん、症状がなくてもご自身で定期的に脈のリズムを測っていただき、脈が乱れている場合はお気軽に当院までご相談ください。
成人先天性心疾患
先天性心疾患とは、胎児期に心臓や血管の形成に問題が生じ、生まれつき心臓に異常がある状態です。幼児期に手術などで心内修復術を受けている方もいれば、未修復で経過観察されている方もいらっしゃいます。以前は、先天性心疾患の新生児は成人に達することが出来ないことも多かったですが、近年では手術療法やカテーテル治療の技術が進歩したことで、9割近くの患者さまは成人を迎えられるようになってきました。幼初期に心臓の治療を行うことで、小児期から青年期にかけて安定した経過を辿りますが、成人に達すると心不全や不整脈といった様々な問題が生じてくることが近年分かってきました。そのため成人期に達した先天性心疾患のことを成人先天性心疾患(ACHD)と呼ぶようになりました。主な疾患は心房中隔欠損症、心室中隔欠損症、ファロー四徴症、修正大血管転位症やフォンタン手術後などです。ACHDは患者さま個々で心臓の病気が異なり、治療法も違います。また成人期における様々なライフイベント (仕事や家庭や育児に出産など)も考慮しながら、心疾患の管理を行う必要があります。診療には専門的な知識や経験が必要となり、当院院長は成人先天性心疾患専門医であります。ご自身のご病気のことや治療方法、ライフイベントとの両立の仕方についてご相談したいことがありましたらお気軽に当院までお越しください。
肺高血圧症
肺高血圧症とは、心臓から肺に血液を送る血管である肺動脈の血流が阻害されることで、肺動脈の血圧が上昇する病気です。主な症状は、全身のだるさや息切れ、足のむくみ、喀血、失神などです。
疑わしい症状が現れた際には、心電図検査や血液検査、胸部レントゲン検査、心エコー検査などを実施して詳しい状態を確認します。これらの検査によって、肺高血圧症の可能性が高いと判断した場合は、右心カテーテル検査を実施して更に詳しい状態を調べます。なお、右心カテーテル検査が必要と判断した際は、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
肺血栓塞栓症
肺血栓塞栓症とは、静脈のどこかで血栓が生じ、それによって肺や心臓の血管が閉塞してしまう病気です。主な症状は、胸痛や呼吸困難などで、中には突然命を落とすこともあるため、発症したら緊急治療が必要となります。なお、当院では入院治療が必要と判断した際には、速やかに連携する高度医療機関をご紹介いたします。
大動脈疾患
大動脈解離
大動脈解離とは、大動脈を構成する内膜、中膜、外膜の3層構造のうち、内膜が縦方向に裂けて中膜に血液が流入することで大動脈も裂けてしまう病気です。通常であれば、内膜は十分な強度を持っていますが、高血圧や動脈硬化などが原因で内膜が弱体化することが発症原因と考えられています。症状は血管が裂けるために生じる激しい痛み、胸痛や腹痛もしくは移動する痛みがあり、時に脳への血液が途絶えて失神を起こすことがあります。
心臓の近くである上行大動脈が解離した場合はStanford A型大動脈解離といい、緊急手術が必要となります。上行大動脈以外が解離し、上行大動脈が解離していない場合はStanford B型大動脈解離といい、緊急入院の上で薬物治療を行います。なお、当院では入院治療が必要と判断した際には、速やかに連携する高度医療機関をご紹介いたします。
大動脈瘤
大動脈瘤とは何らかの原因によって大動脈の壁が薄くなって膨張している状態の病気です。初期の段階ではほとんどの場合自覚症状に乏しいため、健診などの胸部レントゲン検査の際に偶然発見されることが多いです。中には、膨張した大動脈が周囲の神経を圧迫して声がかすむなどの症状が現れる他、腹部に触れた際に直接確認できることもあります。治療せずに放置すると、大動脈が破裂して激しい胸痛や腰痛、意識障害などを起こして死に至るとても危険な病気です。そのため、早期発見と早期治療が重要な病気です。
大動脈瘤はCT検査を用いて動脈瘤の大きさを定期的に測定します。動脈瘤が非常に大きい場合や痛みなどの症状増悪が見られた際には、動脈瘤破裂の疑いがあるため、早急にカテーテル治療や手術治療を行います。なお、当院では手術療法が必要と判断した際は、速やかに連携する高度医療機関をご紹介いたします。また、大動脈瘤は様々な危険因子が複合的に重なって発症することが多いため、治療後も生活習慣の改善や体調管理に気をつけ、慎重に経過観察を行うことが大切です。
閉塞性動脈硬化症
閉塞性動脈硬化症とは、動脈硬化によって血流が阻害されることで様々な症状を引き起こす病気です。下肢動脈に症状が現れることが多く、60歳以上の喫煙習慣のある男性に多く見られる傾向があります。
初期の段階では下肢の痺れや冷感の他に、間欠性跛行 (運動時に痛みを生じ、休むと痛みが改善する)が症状として現れるのが特徴です。重症化すると潰瘍や下肢の壊死などを引き起こし、最悪の場合下肢の切断を余儀なくされることがあります。気になる症状がある場合にはお気軽に当院にご相談ください。
深部静脈血栓症
深部静脈血栓症とは、主に下肢静脈が血栓によって閉塞を起こす病気です。血栓は足の表面やふくらはぎ、膝、太もも、骨盤部など様々な部位に現れます。特に、骨盤部や太ももの深部静脈が血栓によって閉塞を起こすと重症化する可能性があるため注意が必要です。
症状は血栓によって静脈の血液がうっ滞するために、同部位の下肢のむくみが強く出てきます。
また、血栓が血流に乗って肺の血管が閉塞を起こすと肺血栓塞栓症を併発することもあります。肺塞血栓栓症を起こすと、胸痛や呼吸困難、失神の他、中には突然死することもあるため、入院治療が必要になります。なお、当院では入院治療が必要と判断した場合には、速やかに連携する高度医療機関をご紹介いたします。
高血圧
血圧とは血管にかかる圧力を示す指標で、高血圧はこの圧力によって慢性的に血管に負担がかかった状態です。日本では40歳以上の男性で約60%、女性で約40%が高血圧であるという報告もあり、国民病とも言える病気の一つとなっています。
高血圧状態が長期間継続すると、全身の血管がダメージを受けて動脈硬化を進行させ、脳卒中や心筋梗塞など様々な病気を引き起こす恐れがあります。そのため、健診などで高血圧を指摘された場合は、できるだけ早い段階で生活習慣を改善すると共に、頸動脈エコー検査や足関節上腕血圧比 (ABI検査)などで動脈硬化の状態を把握することが大切です。
糖尿病
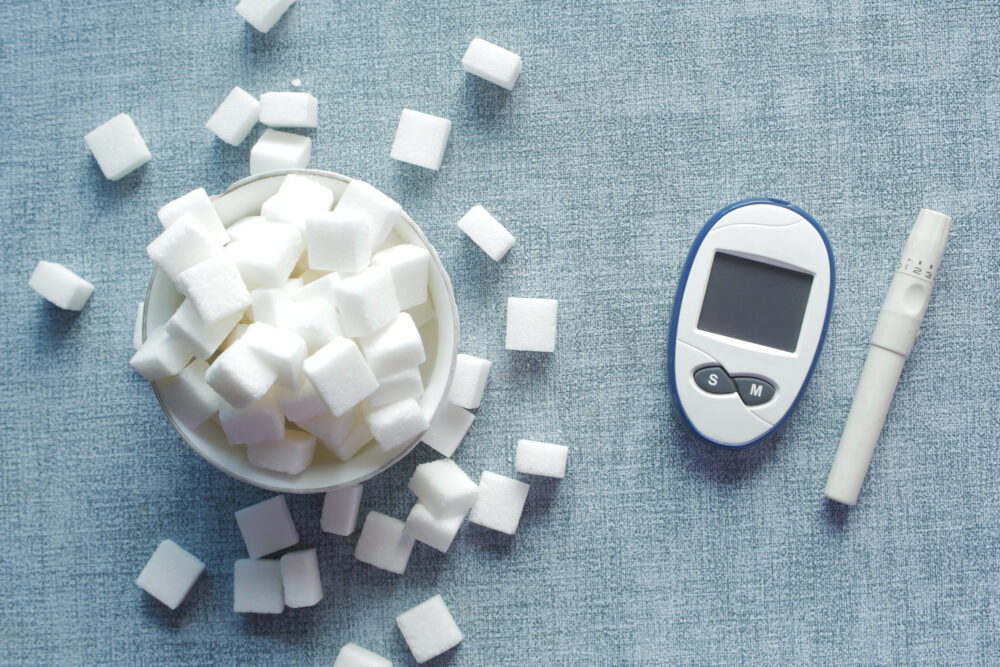 糖尿病とは、体の中で血糖をエネルギーとして使うためのインスリンというホルモンが十分に働かなくなることが原因で血液中の糖(血糖)が慢性的に高くなる病気です。基本的に糖尿病は症状がありません。しかし糖尿病のコントロールが不良のままにしていると、体のさまざまな器官がダメージを受け、健康に大きな影響を及ぼします。特に血糖値が高い状態が続くと、血管に負担がかかり、動脈硬化が進行します。この動脈硬化が原因で狭心症や心筋梗塞といった心臓病を引き起こしやすくします。また心臓の筋肉にも負担がかかり心不全になるリスクが高まります。そのため糖尿病と診断された場合には、食習慣の改善や運動療法、薬物療法などによって血糖値を適切に保つことと共に、NT-proBNPといった心不全マーカーや心エコー検査を用いて心臓の機能を定期的に評価することが重要です。
糖尿病とは、体の中で血糖をエネルギーとして使うためのインスリンというホルモンが十分に働かなくなることが原因で血液中の糖(血糖)が慢性的に高くなる病気です。基本的に糖尿病は症状がありません。しかし糖尿病のコントロールが不良のままにしていると、体のさまざまな器官がダメージを受け、健康に大きな影響を及ぼします。特に血糖値が高い状態が続くと、血管に負担がかかり、動脈硬化が進行します。この動脈硬化が原因で狭心症や心筋梗塞といった心臓病を引き起こしやすくします。また心臓の筋肉にも負担がかかり心不全になるリスクが高まります。そのため糖尿病と診断された場合には、食習慣の改善や運動療法、薬物療法などによって血糖値を適切に保つことと共に、NT-proBNPといった心不全マーカーや心エコー検査を用いて心臓の機能を定期的に評価することが重要です。
脂質異常症(高脂血症)
脂質異常症(高脂血症)とは、脂質の多い食事習慣などによって血液中の中性脂肪やコレステロールが慢性的に上昇している状態の病気です。脂質異常症(高脂血症)は、悪玉コレステロールであるLDLコレステロールが多い高LDLコレステロール血症、中性脂肪が多い高トリグリセライド(TG)血症、善玉コレステロールであるHDLコレステロールが少ない低HDLコレステロール血症の3種類に分類されます。発症すると、過剰な中性脂肪やコレステロールが血流を阻害することから全身の動脈硬化を進行させ、脳卒中や心筋梗塞などの重篤な合併症を引き起こす恐れもあります。
脂質異常症(高脂血症)の主な原因は生活習慣の乱れです。また女性の場合、更年期や閉経後にホルモンバランスの問題で脂質異常症を発症することが多いです。健診などで脂質異常症を指摘された場合は、できるだけ早い段階で生活習慣の見直しをすると共に、頸動脈エコー検査や足関節上腕血圧比 (ABI検査)などで動脈硬化の状態を把握することが大切です。
睡眠時無呼吸症候群
睡眠時無呼吸症候群とは、就寝中に一時的に無呼吸状態に陥ってしまう病気です。アジア人に多く見られる傾向があり、日本では1000万人以上が発症しているという報告もあります。一般的に、肥満や加齢によって引き起こされますが、中には顎が小さい方や喉が狭い方にも見られます。
睡眠時無呼吸症候群を発症すると、睡眠時に熟睡できなくなる、酸素欠乏に陥る、自律神経のバランスが乱れ、日中常に眠くなったり判断力が低下したりするなどの症状を引き起こします。また、症状が長期間継続すると、高血圧や脂質異常症、糖尿病などを合併するリスクが高くなる他、心筋梗塞や不整脈、脳梗塞など命の危険を伴う重篤な病気を引き起こす恐れもあるため注意が必要です。
睡眠時無呼吸症候群は、簡易終夜睡眠ポリグラフ検査 (PSG検査)という自宅で出来る検査によって発症の有無を確認でき、CPAPを使用して自宅で治療することも可能です。家族などからいびきを指摘された場合にはできるだけお早めに当院までご相談ください。
循環器内科での主な検査
血液検査
血液検査では、血糖、HbA1cや中性脂肪、コレステロールなどの値を調べることで、糖尿病や脂質異常症などの循環器疾患の発症リスクを確認することができます。また、心不全や心筋梗塞などの病気が疑われる場合は、NT-proBNPや心筋トロポニン値の検査を行います。
心電図検査
心電図検査とは、身体に電極を取り付けて心臓の状態を調べる検査です。狭心症や心筋梗塞、不整脈などの病気の検査が出来ます。心電図検査の結果に異常がある場合や、動悸や胸痛、脈拍異常などの症状が現れている場合は、狭心症や心筋梗塞、不整脈などの病気の可能性がありますので、お早めにご相談ください。
ホルター心電図検査
ホルター心電図検査とは、小型の検査機器を身体に取り付けることで心拍を24時間から最大5日間記録する検査です。日常生活を送りながら心拍の状態を長時間確認することができます。
通常の心電図検査では計測時間が短いため、検査中にたまたま異常が出なかった場合に不整脈などの病気を見逃してしまう恐れがあります。そのため、何らかの病気が疑われる場合には、ホルター心電図検査を行い、長時間心拍の状態を確認する必要があります。
胸部レントゲン検査
胸部レントゲン検査は、肺や心臓、大動脈の状態を確認できる画像検査です。肺うっ血や心拡大、胸水、心不全など様々な病気の有無を確認することが可能です。
エコー検査
頸動脈エコー検査
頸動脈エコー検査とは、首付近に超音波を当てることで頸動脈の血管や血流、血栓の有無、動脈硬化の進行度合いなどを確認する検査です。頸動脈は脳に血液を送る重要な動脈のため、この頸動脈が動脈硬化によって狭窄や閉塞を起こすと、脳梗塞や脳塞栓などの重篤な脳血管疾患を引き起こす恐れがあります。また、頸動脈の動脈硬化が進行している場合は、心臓の冠動脈など他の動脈も動脈硬化を起こしている恐れがあるため、高血圧や脂質異常症、糖尿病などが疑われる場合にも有効な検査です。
心エコー検査
心エコー検査とは、胸部に超音波を当てることで心臓の状態を確認することができる検査です。心臓の動きやサイズ、血流の状態などを調べることができ、心筋症や心臓弁膜症、心筋梗塞、心臓の先天性疾患など様々な心疾患を確認することが可能です。
また、心疾患の治療の際に、治療法の選定や治療効果の確認、手術のタイミングなどを行う際にも有効な検査ですが、正しい検査をするためには経験と検査技術が必要です。さらに検査によって得られた結果から治療法を判断するためには専門的な知識が必要となります。当院は心エコー検査の経験が豊富な医師と検査技師によって心エコー検査を行い、循環器専門医によって治療法を判断しております。当院がもっとも大切にしている検査の一つとなります。
足関節上腕血圧比 (ABI検査)、脈波伝播速度(baPWV検査)
足関節上腕血圧比 (ABI検査)とは、上腕と足首の血圧の比率を表す検査です。正常な状態では上腕の血圧は足首に比べて低い値を示しますが、下肢の動脈が狭窄や閉塞を起こしていると足首の血圧が低下してABIの比率が低下します。閉塞性動脈硬化症の診断に用いられます。
脈波伝播速度(baPWV)検査は心臓の拍動が上腕から足首に伝わる速度 (脈波伝播速度)を調べる検査です。動脈の硬さによって拍動の伝わり方が異なることを利用し、動脈硬化の進みぐらいを検査します。baPWVの高値は一般的に血管年齢が高いと考えられます。