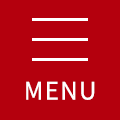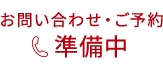不整脈とは
 不整脈とは、心臓の拍動をコントロールしている電気信号に異常が生じることで、心臓の拍動リズムが乱れる病気です。通常、心拍は心臓の洞結節から発生・伝達される電気信号によって、適切なリズムを維持しています。しかし、何らかの原因によってこの電気信号が異常を起こすと、心拍リズムが乱れ、脈が遅くなる徐脈や早くなる頻脈、脈が飛ぶ期外収縮などを引き起こします。
不整脈とは、心臓の拍動をコントロールしている電気信号に異常が生じることで、心臓の拍動リズムが乱れる病気です。通常、心拍は心臓の洞結節から発生・伝達される電気信号によって、適切なリズムを維持しています。しかし、何らかの原因によってこの電気信号が異常を起こすと、心拍リズムが乱れ、脈が遅くなる徐脈や早くなる頻脈、脈が飛ぶ期外収縮などを引き起こします。
不整脈には様々な原因があり、無症状の場合もあれば、重篤な病気の一症状として現れている場合もあるため注意が必要です。
不整脈の有無は、主に心電図検査や心エコー検査によって調べることができます。これらの検査によって不整脈の原因を特定し、最適な治療法を検討していきます。
健康診断で心房細動を指摘された方へ
心房細動とは、心房が震えるように痙攣を起こすことで脈拍が乱れる病気です。一般的に高齢者に多く見られ、近年増加傾向にある病気の一つとなります。高齢者以外では、高血圧や虚血性心疾患、心不全、心臓弁膜症などの病気の合併症としても多く見られます。
心房細動の主な症状は、動悸や息切れ、めまい、胸の違和感などが挙げられますが、中には無症状の場合もあります。しかし、長期間放置すると心不全や脳梗塞を起こすこともあり、注意が必要です。
不整脈や心房細動を指摘された場合は、自己判断で放置せずにできるだけ早めに医療機関を受診し、精密検査や治療を行うことが重要です。
心房細動によって脳梗塞になる?
心房細動の主な症状は、初期の段階では動悸や息切れ、めまい、胸の違和感などで、中には無症状の場合もあります。しかし、心房細動になっていると、心房は痙攣しているために上手く血液を流せず、心房内に血液が滞留し、血栓となります。その血栓が血流に乗って脳に飛んでいってしまうと、脳梗塞を引き起こしてしまいます。そのため、健診などで不整脈や心房細動が疑われた場合には、できるだけ早い段階で治療を開始することが重要です。
心房細動によって心不全になる?
心房細動になっていると、心房は痙攣しているために上手く血液を流せず、心臓が血液を送るための効率は低下してしまいます。その結果心不全が発症するリスクが上がっていきます。そのため早期に心房細動を正常な脈に戻すための治療であるカテーテルアブレーション治療 (肺静脈隔離術)を行うことで、心不全の予防が出来、長期的な目線でもメリットが高いことが知られています。そのため、健診などで不整脈や心房細動が疑われた場合には、アブレーション治療を含めた治療検討が重要です。当院でアブレーション治療が必要と判断された場合は、連携する高度医療機関をご紹介いたします。
生活習慣病は心房細動になりやすい?
高血圧
高血圧は心房細動の発症リスクを高める上、脳梗塞など重篤な合併症を引き起こす恐れもあります。血圧が高めと指摘された場合には、できるだけ早い段階で治療を開始し、症状を改善させることが大切です。
糖尿病
糖尿病は、様々な合併症を引き起こすことで有名な生活習慣病ですが、合併症の一つとして心房細動を引き起こす恐れもあります。実際に、心房細動の患者さまが糖尿病を併発している場合は多く見られます。また糖尿病の患者さまは心房細動の脳梗塞の高リスクとして知られていますので、心房細動の正しい治療が必要となります。
脂質異常症
脂質異常症とは、脂質の多い偏った食事習慣を長期間継続することにより、過剰となったコレステロールや中性脂肪が血液中に蓄積する生活習慣病です。過剰となったコレステロールが、血管にダメージを与えることで動脈硬化を引き起こし、心房細動を合併することもあります。
不整脈の種類
不整脈の症状は細かく分類すると多岐に渡りますが、主に脈が早くなる頻脈、脈が遅くなる徐脈、脈が飛ぶ期外収縮の3種類に分類されます。
頻脈性不整脈
頻脈性不整脈は心拍数が高くなることにより心臓が効率よく血液を送ることが出来なくなる状態をしめします。何かしらの原因によって、心拍を適切なリズムに維持している電気信号の発生や伝達に異常が生じるためと考えられています。
原因や症状によって、心房細動や心房頻拍、心室頻拍、心室細動、発作性上室性頻拍、WPW症候群などに分類されます。特に、心室頻拍や心室細動は命の危険を伴う病気で、致死性不整脈と呼ばれており、注意が必要です。
徐脈性不整脈
心拍数が毎分50回以下になると徐脈性不整脈と診断されます。主な徐脈性不整脈として、洞不全症候群や房室ブロックが挙げられます。主な原因は、心拍を適切なリズムに維持している電気信号の発生や伝達に異常が生じ、心拍が遅くなるためと考えられています。脈が遅くなりめまい感、失神や労作時息切れが生じる場合はペースメーカー治療の適応になる場合があります。
期外収縮不整脈
期外収縮不整脈とは、心拍を適切なリズムに維持している電気信号の発生や伝達に異常が生じ、本来とは異なる場所やタイミングで電気信号が発生してしまうことで、脈が飛ぶなどの症状を引き起こす不整脈です。症状によって心房性期外収縮や心室性期外収縮などに分類されます。
主な原因は、過度な飲酒や喫煙、過労などと共に、心筋症などの心臓の機能が低下している部分から生じることが多いです。薬剤治療やカテーテルアブレーション治療などが選択肢としてあげられていきますが、その選択にはご自身の心機能との兼ね合いにより変化します。気になる症状がある場合は、お気軽に当院にご相談ください。
不整脈の原因はストレス?
不整脈を引き起こす原因は様々あり、中には原因が不明なこともあります。主な原因は以下となります。
心疾患によるもの
狭心症
 狭心症とは、何らかの原因によって心臓に酸素を運搬する冠動脈の血流が阻害され、心臓の筋肉が酸素不足となる病気です。主な原因は、動脈硬化によって冠動脈が損傷することが考えられています。
狭心症とは、何らかの原因によって心臓に酸素を運搬する冠動脈の血流が阻害され、心臓の筋肉が酸素不足となる病気です。主な原因は、動脈硬化によって冠動脈が損傷することが考えられています。
主な症状は、運動時の胸痛や放散的な左肩痛、動悸、歯の痛みの他、胃痛やみぞおち痛を起こしている場合は吐き気などを伴うこともあります。ほとんどの場合は安静にすると数分 (2〜3分程度)で治りますが、中には長時間症状が継続することもあります。
また、狭心症はより重篤な不整脈系疾患へと進行する恐れもあるため、気になる症状が現れている場合は、できるだけ早い段階で医療機関を受診し、検査や治療を行うことが大切です。
心筋梗塞
心筋梗塞とは、動脈硬化などによって冠動脈が閉塞を起こし、心筋が壊死する病気です。心筋梗塞が原因で、徐脈性不整脈や心室細動、心室頻拍、心室性期外収縮などの不整脈が引き起こされることがあります。
主な症状は、30分以上続く激しい胸痛や嘔吐、呼吸困難、冷汗などになります。ただし、高齢者や糖尿病の罹患者は胸痛があまり生じない場合もあるため、少しでも違和感が生じたらできるだけ早めに医療機関を受診し、検査を行うことが大切です。
心不全
心不全とは、加齢や病気などが原因で心臓機能が低下し、全身への血液の運搬力が不足して呼吸困難など様々な症状を引き起こす病気です。血液が上手に送れず、心臓への負担が高まってくると不整脈が現れる特徴もあります。
心不全には、心筋梗塞などで突然心臓の機能が低下し、発症する急性心不全とゆるやかに心臓の機能低下が進行する慢性心不全があります。
主な症状は、急性心不全の場合は激しい呼吸困難、横になれない強い息切れなどがあります。慢性心不全の場合は動悸や全身のむくみ、運動時の息切れ、倦怠感などが挙げられますが、心不全の治療が不十分ですと、慢性心不全が急性増悪し、急性心不全のように強い呼吸困難が突然生じる場合があります。
心臓弁膜症
心臓弁膜症とは、心臓内の4つの部屋を隔てる弁の働きに異常が起きる病気です。弁は4つの部屋の中で血液の逆流を防いだり、全身に血液を適切に送り出したりする役割を担っています。そのため、心臓弁膜症になると不整脈や息切れ、全身倦怠感、むくみなど様々な症状を引き起こします。
主な原因は、加齢や先天性異常の他、動脈硬化や心筋梗塞、リウマチ熱など他の病気の合併症として引き起こされることもあります。
初期の段階では薬物療法によって改善が見込めますが、重症化した場合は手術療法が検討されることもあります。なお、手術が必要と判断された場合は、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
生活習慣によるもの
運動不足
不整脈は自律神経 (交感神経と副交感神経)のバランスの乱れによって生じるとされています。心臓の機能が悪いと交感神経が活性化しますが、この交感神経が有意な状態が続くことで心臓の筋肉の障害が進むとされています。そのため交感神経を抑え、副交感神経を有意にすることが大切です。運動、とくに有酸素運動は自律神経のバランスを整えることに効果的とされ、適度に運動習慣を取り入れることで、心筋の働きを活性化して心肺機能を高めることができます。
運動は、初期の段階では無理のない範囲で、軽いウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動から始めてみましょう。運動習慣は長期間継続することが重要ですので、最初のうちは軽いメニューから始め、体が慣れてきたら徐々に運動量を増やしていくようにしましょう。
飲酒
飲酒と不整脈には強い相関関係があることが報告されています。また、近年では1日1杯程度の飲酒習慣でも、不整脈の発症リスクが向上するという研究結果もあります。
そのため、飲酒習慣がある方は過度な飲酒を控えることはもちろんのこと、適度の休肝日や節酒期間を設けて心臓を休ませることが大切です。
カフェインと喫煙
カフェインの過剰摂取や喫煙も不整脈を引き起こす要因となります。日頃から仕事などでコーヒーや緑茶を多く摂取する習慣がある方は、量を減らしたりカフェインレスの飲料水に変更したりするなどの工夫をしましょう。
また、喫煙は不整脈だけでなく数多くの病気の原因となりますので、長期間喫煙習慣がある方は、禁煙を心がけるようにしましょう。
過剰なストレスや睡眠不足
過度なストレスの蓄積や睡眠不足に陥ると、自律神経のバランスが乱れて心拍が不規則になり、不整脈を引き起こします。
そのため、日頃から上手にストレスを発散したり、十分な睡眠時間を確保したりすることが不整脈の予防には大切です。
加齢
加齢によって心臓内の電気信号の伝達機能が低下したり、異常な電気信号の通り道が生じたりすると、不整脈を引き起こします。
不整脈の症状
不整脈は、脈が遅くなる徐脈、脈が速くなる頻脈、脈が飛ぶ期外収縮の3つのタイプに大きく分かれ、現れる症状もそれぞれ異なります。
徐脈の場合はめまいやふらつき、意識障害などの症状があり、頻脈の場合は吐き気や冷や汗、胸痛、意識が遠のくなどの症状が挙げられます、一方、期外収縮は無症状の場合が多いですが、中には胸痛や胸の不快感などの症状が現れることがあります。
不整脈の検査・診断
心電図検査
心電図検査は、身体に電極を取り付けることで心拍の状態を確認することができる検査です。不整脈の特徴的な症状が現れている場合は、心電図検査にも異常が検出されます。
ただし、心電図検査を行っている最中に不整脈の症状が現れない場合は、見逃されてしまう恐れもあります。そのため、不整脈が疑われる場合は、後述のホルター心電図検査を行うこともあります。
ホルター心電図検査
ホルター心電図検査とは、身体に取り付けることで最長5日間の心拍の状態を確認することができる検査機器です。主に不整脈が疑われる場合に使用します。
検査機器は小型のため、身体に取り付けながら通常の生活を送ることが可能です。また、取り付けたままシャワーを浴びることもできます。
胸部レントゲン検査
胸部レントゲン検査とは、心臓や肺、大動脈などの状態を確認することができる画像検査です。不整脈によって心拡大、肺うっ血や胸水などが生じていないかを調べることができます。ただし、レントゲン検査は放射線を使用するため、微細な被ばくリスクがあります。
心エコー検査
心エコー検査とは、身体に超音波を照射することで心臓の状態を確認することができる画像検査です。放射線を使用しないため、被ばくリスクはなく、痛みも伴わないため、患者さまの負担なく繰り返し行うことができます。
そしてなにより心臓の動きや血液の流れを視覚的に確認できるために、心臓の状態を知る上では最も有用な検査として考えられます。不整脈時の心臓の機能、心臓弁膜症の有無、心不全の有無、心内血栓の有無などあらゆる情報を確認することができます。
不整脈の治療
 不整脈を起こしても、全ての場合で治療が必要というわけではありません。不整脈の種類や頻度、患者さまの心臓の機能によって治療法の選択を行います。一般的に心室性期外収縮の場合は動悸などの症状が強く、日常生活に支障が出ている場合は薬物治療を選択しますが、心室期外収縮の頻度が高い場合 (1日総心拍数の10%程度以上)や心機能が低下している場合にはカテーテルアブレーション治療も検討されます。また心房細動の場合も以前は薬物治療だけで見ることが多かったですが、近年薬物治療よりカテーテルアブレーション治療を行った方が心不全や脳梗塞の予防の観点からも良好な成績が出てきております。不整脈治療は患者さまの状態に合わせて最適なタイミングで最適な治療法を選択することが重要となります。当院で実施している不整脈の治療は薬物療法になりますが、アブレーション治療が最適な患者さまには、連携する高度医療機関をご紹介いたします。
不整脈を起こしても、全ての場合で治療が必要というわけではありません。不整脈の種類や頻度、患者さまの心臓の機能によって治療法の選択を行います。一般的に心室性期外収縮の場合は動悸などの症状が強く、日常生活に支障が出ている場合は薬物治療を選択しますが、心室期外収縮の頻度が高い場合 (1日総心拍数の10%程度以上)や心機能が低下している場合にはカテーテルアブレーション治療も検討されます。また心房細動の場合も以前は薬物治療だけで見ることが多かったですが、近年薬物治療よりカテーテルアブレーション治療を行った方が心不全や脳梗塞の予防の観点からも良好な成績が出てきております。不整脈治療は患者さまの状態に合わせて最適なタイミングで最適な治療法を選択することが重要となります。当院で実施している不整脈の治療は薬物療法になりますが、アブレーション治療が最適な患者さまには、連携する高度医療機関をご紹介いたします。
薬物療法
頻脈性不整脈の場合は、心臓の電気信号の発生を抑制する薬を使うことで脈を正常なスピードに整え、症状を緩和させます。また心臓の細胞に伝わる電気の速度を変えることで不整脈自体の発生を抑えます。
カテーテルアブレーション
カテーテルアブレーションとは、不整脈の原因となる異常な電気信号を発生している心臓の筋肉や電気回路を焼灼 (アブレーション)し、不整脈を起こさせなくする治療法です。心臓の筋肉を焼灼するために、カテーテルという医療機材を足 (鼠径部)にある静脈という血管から挿入し、心臓にまで運びます。血管の中を通って心臓まで運ぶために、開胸する必要がなく、低侵襲で行える治療法です。主に、頻脈性不整脈の治療に適用されます。なお、当院ではカテーテルアブレーションは実施しておりませんので、必要と判断された場合は、連携する高度医療機関をご紹介いたします。
ペースメーカー
ペースメーカーとは、体内に専用の装置を埋め込んで心臓に電気信号を加え、心臓の拍動を活性化させたり、適正スピードに整えたりすることができる検査機器です。主に徐脈性不整脈の治療の際に使用されます。
なお、ペースメーカーを使用する際には、ペースメーカー外来のある医療機関を定期的に受診し、検査機器のチェックや経過観察を行う必要があります。当院のペースメーカー外来では検査機器の埋め込み手術は実施しておりませんが、他院で埋め込み手術を行った患者さまの経過観察を行っています。どうぞご相談ください。
植込み型除細動器(ICD)
植込み型除細動器とは、心臓が異常な電気信号を発生して頻脈性不整脈を引き起こした際に、自動で電気ショックを与えて心拍を正常なスピードに整える埋め込み式の治療機器です。主に心室細動や心室頻拍などによって、突然死のリスクがある患者さまに適用します。
なお、当院では植込み型除細動器の治療は実施しておりませんので、必要と判断された場合は、連携する高度医療機関をご紹介いたします。
脈拍のセルフチェック
以下は、ご自身で行える脈拍のセルフチェック法です。気になる症状が現れている場合や不整脈の疑いがある場合には、ぜひ以下の手順で脈拍のセルフチェックを行ってみてください。
- 手の平を上向きにします。
- 親指側の手首を、薬指・中指・人差し指の3本の指で軽く押さえます。
- 15秒程度脈拍の速度を確認します。
- 徐脈や頻脈を感じたら、1~2分間継続して測定します。
- 1〜4の手順でチェックを行い不規則な脈拍を感じた場合は、心房細動などの病気の疑いがあります。その際には、できるだけ早い段階で当院までご相談ください。