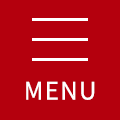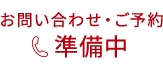虚血性心疾患とは
 虚血性心疾患とは、動脈硬化によって心臓の血管が狭窄を起こし、心臓の筋肉が酸素不足に陥る病気です。運動時に心臓の筋肉が酸素不足となると、胸痛や胸部の違和感などの症状を引き起こします。また慢性的に心臓の筋肉が酸素不足になっていることで心臓の機能が低下し、心不全を引き起こす場合があります。症状は労作時の胸部圧迫感や違和感が知られていますが、中には歯痛や肩こりのような胸痛とは異なる症状があるため注意が必要です。
虚血性心疾患とは、動脈硬化によって心臓の血管が狭窄を起こし、心臓の筋肉が酸素不足に陥る病気です。運動時に心臓の筋肉が酸素不足となると、胸痛や胸部の違和感などの症状を引き起こします。また慢性的に心臓の筋肉が酸素不足になっていることで心臓の機能が低下し、心不全を引き起こす場合があります。症状は労作時の胸部圧迫感や違和感が知られていますが、中には歯痛や肩こりのような胸痛とは異なる症状があるため注意が必要です。
初期の段階では自覚症状に乏しく、健診で心電図検査が異常を指摘されて初めて気づくことも多く見られます。
主な虚血性心疾患として、狭心症や心筋梗塞が挙げられます。
狭心症
狭心症とは
狭心症とは、心臓の筋肉に酸素を運搬する冠動脈が動脈硬化などが原因で狭窄を起こしている状態の病気です。主な症状は、動悸や息切れ、胸焼け、胸の圧迫感、吐き気、冷や汗などが挙げられます。歯痛や肩こりのような胸痛とは異なる症状もあるため注意が必要です。
狭心症は、病状によって安定性狭心症、不安定狭心症、冠攣縮性狭心症の3つのタイプに分類され、特に不安定性狭心症になると、心筋梗塞を起こす一歩手前の段階のため注意が必要です。
安定性狭心症
安定性狭心症は、主に運動時のみに症状が現れるタイプの狭心症です。動脈硬化によって血管内にはプラークと言われる成分が蓄積し、血管は狭くなっています。このプラークが破綻すると血管内の血液の流れが極端に低下し、心筋梗塞となります。このプラークが安定している状態を安定性狭心症といいますが、脂質異常症、高血圧、糖尿病、喫煙などのコントロールが十分でないとプラークが不安定化し、不安定狭心症へと変わっていきます。
不安定狭心症
不安定性狭心症は、軽い運動時や安静時にも症状が現れるタイプの狭心症です。1日のうち、何度も狭心症発作を起こすことがあります。血管内にあるプラークが非常に不安定であり、破綻する可能性が高い状態です。そのため不安定性狭心症は心筋梗塞を起こす一歩手前の状態のため、早急に治療する必要があります。
冠攣縮性狭心症
冠攣縮性狭心症は、プラークによる冠動脈の狭窄が無いにもかかわらず、副交感神経の活性により冠動脈が一時的に過剰収縮 (攣縮)を起こしてしまう病気です。副交感神経との関与が言われているために、主に就寝中などの安静時に生じることが多いです。薬物治療によってコントロールしますが、強い攣縮が起きると心筋梗塞になる場合があります。朝方の胸部絞扼感を繰り返す場合は一度ご相談ください。
狭心症の原因
 狭心症の原因の多くは動脈硬化です。動脈硬化とは、加齢や生活習慣の乱れなどによって動脈が硬化し、血管内に血栓やプラークが蓄積して血管が狭窄や閉塞を起こす状態です。
狭心症の原因の多くは動脈硬化です。動脈硬化とは、加齢や生活習慣の乱れなどによって動脈が硬化し、血管内に血栓やプラークが蓄積して血管が狭窄や閉塞を起こす状態です。
特に、脂質の多い食事習慣や運動不足、肥満、喫煙などの乱れた生活習慣を長期間継続すると、動脈硬化のリスクが高まるため注意が必要です。高血圧、脂質異常症、糖尿病の管理と共に生活習慣を整えることが大切です。
狭心症の症状
狭心症の主な症状は、動悸や息切れ、胸焼け、胸の圧迫感、吐き気、冷や汗などです。ただし、病状の進行度合いによってこれら症状の発生時期や症状が続く時間は異なります。
一般的に、安定性狭心症の場合は安静にすると数分程度で自然に治まります。しかし不安定性狭心症まで進行すると、安静にしてもなかなか症状が治まらず、治まったとしても1日のうちに何度も現れるようになります。一方、冠攣縮性狭心症の場合は30分以上症状が継続することがあります。不安定性狭心症は、冠動脈が閉塞して心筋梗塞を起こす一歩手前の状態のため、早急に医療機関を受診して治療を開始する必要があります。
狭心症の検査
血液検査
血液検査は、狭心症の有無を調べる上で最も簡単に行える検査です。特に心筋トロポニンT検査は特異度の高い検査となります。ただし、初期の段階では狭心症の症状も軽度なため、血液検査を行っても異常が現れずに見逃されてしまう場合もあります。
心電図検査
心電図検査は、身体に電極を取り付けて心拍の状態を調べる検査です。検査中に狭心症の特徴的な症状が現れた場合は、心電図検査に異常が検出されて狭心症と診断できます。しかし、検査中に症状が現れない場合は見逃されてしまうこともあります。
心エコー検査
心エコー検査とは、胸部に超音波を照射して心臓の動きや異常の有無を確認する検査です。一般的に狭心症などにより心筋が虚血になった場合に、採血検査や心電図検査で異常が生じてくるよりも早くに心筋の動きの低下が生じてくるとされています。そのため心エコー検査によって心臓の動きの異常を見つけることで、狭心症などの虚血性心疾患を見つけに行きます。
心臓CT検査
心臓CT検査とは、造影剤を使って心臓の冠動脈が狭窄や閉塞を起こしていないかを確認することができる検査です。心臓CT検査が必要と判断した場合は、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
心臓カテーテル検査
心臓カテーテル検査とは、手首や足からカテーテルを挿入して冠動脈に造影剤を注入し、冠動脈の狭窄や閉塞の有無を確認する検査です。心臓カテーテル検査が必要と判断した場合は、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
狭心症の治療
狭心症の主な治療は薬物療法とカテーテル療法と手術療法で、病状によって治療法を検討します。不安定狭心症や心筋梗塞の場合、カテーテルを使用して冠動脈を治療するカテーテル・インターベンション(PCI)を行います。複数の血管に狭窄がある場合や過去にPCIで治療しながらも再発を繰り返している場合は、開胸手術による治療を行います。具体的には冠動脈に新しい血管を接続する冠動脈バイパス術を行います。安定狭心症の場合は薬物療法かカテーテル治療を行います。この治療選択は心臓カテーテル検査もしくは冠動脈CT検査を行うことで判断されます。当院は薬物療法のみ対応可能ですので、カテーテル療法や手術療法が必要と判断した場合は連携する高度医療機関をご紹介いたします。
薬物療法
薬物療法では、冠動脈のプラークを安定化させる治療を行います。プラークを安定化させるためにはまずLDLコレステロールを十分に下げ、HDLコレステロールを上げる必要があります。一般的にLDLコレステロールは140mg/dl以上で脂質異常症(高脂血症)の診断となりますが、不安定型狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患の患者さまはLDLコレステロール 70mg/dl以下にする必要があります。そのためHMG-CoA還元酵素阻害剤や小腸コレステロールトランスポータ阻害剤を用いてLDLコレステロールのコントロールを行い、必要に応じてPCSK9阻害剤による自己注射治療を行います。さらに抗血小板剤の内服によりプラークを安定化させます。また薬物療法のみならず、食事療法や運動療法など狭心症の原因となっている生活習慣の改善も同時に行うことが大切です。その他、狭心症を合併する恐れがある高血圧、糖尿病、喫煙などの生活習慣病に罹患している患者さまは、これら病気の治療を行うことも狭心症を予防する上で重要です。
カテーテル・インターベンション(PCI)
カテーテル・インターベンション(PCI)とは、狭窄もしくは閉塞を起こしている冠動脈にステントといわれる金属の筒を置いて冠動脈の血流を再開させる治療です。ステントの表面には薬剤が塗ってあり、この薬の効果でステント内が再度詰まることなく開存し続けてくれます。手首や足 (鼠径部)の動脈からカテーテルを挿入し、カテーテルを用いて冠動脈にステントを運びます。血管の中を通って冠動脈まで運ぶために、開胸する必要がなく、低侵襲で行える治療法です。PCIの治療後は一定期間抗血小板剤を2剤、もしくは抗血小板剤1剤と抗凝固剤1剤を飲みます。時期が来ると減薬しますが、薬を飲まない時期があるとステントが血栓で詰まってしまい再治療が必要になることがありますので、内服は続けてください。
なお、カテーテル・インターベンション(PCI)が必要と判断した場合は、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
冠動脈バイパス移植術
冠動脈バイパス移植術とは、狭窄もしくは閉塞を起こしている冠動脈に新しい血流の道を移植する治療です。これにより、心臓への血流が改善され、正常な状態に戻ります。主に、胸骨の裏にある内胸動脈、腕の橈骨動脈、胃に血液を送る右大網動脈、足の大伏在静脈などを用いて冠動脈に新しい血流の道を作ります。
なお、冠動脈バイパス移植術が必要と判断した場には、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
心筋梗塞
心筋梗塞とは
 心筋梗塞とは、動脈硬化などが原因で心臓の筋肉に酸素を運搬する冠動脈が閉塞を起こし、心筋が壊死してしまう病気です。様々な世代に発症しますが、特に40〜50代に多く見られる特徴があります。
心筋梗塞とは、動脈硬化などが原因で心臓の筋肉に酸素を運搬する冠動脈が閉塞を起こし、心筋が壊死してしまう病気です。様々な世代に発症しますが、特に40〜50代に多く見られる特徴があります。
壊死してしまった心筋は再生されないため、全身に血液を送り出す心臓のポンプ機能が低下し、不整脈や心臓弁膜症、心不全など様々な合併症を引き起こします。中には、心臓の機能が停止し、突然死を招く恐れもあるため注意が必要です。
心筋梗塞の原因
心筋梗塞の原因として最も多いのが、生活習慣の乱れによって引き起こされる動脈硬化です。動脈硬化によって冠動脈内に血栓やプラークが生じ、これらによって血管が完全に閉塞を起こすと心筋梗塞を発症します。
主な原因は、脂質の多い食事習慣や運動不足、肥満、喫煙、過度なストレスの蓄積などの生活習慣の乱れの他、高血圧や脂質異常症、糖尿病などの生活習慣病も心筋梗塞を発症させます。また、血縁者に狭心症や心筋梗塞の罹患歴がある場合は、心筋梗塞の発症リスクが高まるという報告もあります。
その他では、ごく稀に動脈硬化を起こしていないにも関わらず、冠動脈が攣縮して発症する心筋梗塞もあります。
心筋梗塞の初期症状(前兆)
心筋梗塞の主な症状は、突然の激しい胸痛や胸を締め付けられるような圧迫感などで、中には歯や首、肩、腕にまで痛みが放散することもあります。症状は狭心症と類似していますが、狭心症の場合は安静にするとすぐに治まるのに対し、心筋梗塞の場合は痛みが治まらずに持続する特徴があります。
その他では、痛みを伴わずに発症する無痛性心筋梗塞という場合もあります。無痛性心筋梗塞は、一般的に高齢者や糖尿病の患者さまに多く見られます。
心筋梗塞の検査
血液検査
血液検査では、主に心筋トロポニンという酵素の含有量を測定します。心筋梗塞によって心筋が壊死すると、心筋トロポニンが多く分泌されて血液中の含有量が増大します。
心筋トロポニン含有量を調べる検査は、迅速キットを使用するため、短時間で結果を知ることができます。心筋トロポニンが一定以上確認されると陽性判定が出ますが、初期の段階の心筋梗塞では偽陰性が出ることもあります。
心電図検査
心電図検査とは、身体に電極を取り付けて心臓の状態を確認する検査です。急性心筋梗塞の場合は、心電図検査に特徴的な異常が検知されますので、確定診断に繋げることが可能です。
心エコー検査
心エコー検査とは、胸部に超音波を照射して心臓の状態を確認する検査です。レントゲンと違って放射線を使用しないため、被ばくのリスクがなく繰り返し行うことが可能です。心エコー検査を行うことで、心筋梗塞が発生している場所や症状の程度を調べることができ、また心筋梗塞に合併する心臓弁膜症や心不全の有無も診断することが出来ます。
心臓カテーテル検査
心臓カテーテル検査とは、カテーテルを挿入して冠動脈内に造影剤を注入し、冠動脈の状態を確認する検査です。心筋梗塞によって狭窄や閉塞を起こしている冠動脈の場所を特定することが可能です。
なお、心臓カテーテル検査は入院治療となりますので、必要と判断した場合は、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
心筋梗塞の治療
カテーテル・インターベンション(PCI)
カテーテル・インターベンション(PCI)とは、狭窄もしくは閉塞を起こしている冠動脈にステントといわれる金属の筒を置くことで冠動脈の血流を再開させる治療です。ステントの表面には薬剤が塗ってあり、この薬の効果でステント内が再度詰まることなく開存し続けてくれます。手首や足 (鼠径部)の動脈からカテーテルを挿入し、カテーテルを用いて冠動脈にステントを運びます。血管の中を通って冠動脈まで運ぶために、開胸する必要がなく、低侵襲で行える治療法です。PCIの治療後は一定期間抗血小板剤を2剤、もしくは抗血小板剤1剤と抗凝固剤1剤を飲みます。時期が来ると減薬しますが、薬を飲まない時期があるとステントが血栓で詰まってしまい再治療が必要になることがありますので、内服は続けてください。
なお、カテーテル・インターベンション(PCI)が必要と判断した場合は、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
冠動脈バイパス移植術
冠動脈バイパス移植術とは、狭窄もしくは閉塞を起こしている冠動脈に新しい血流の道を移植する治療です。これにより、心臓への血流が改善され、正常な状態に戻ります。主に、胸骨の裏にある内胸動脈、腕の橈骨動脈、胃に血液を送る右大網動脈、足の大伏在静脈などを用いて冠動脈に新しい血流の道を作ります。
なお、冠動脈バイパス移植術が必要と判断した場には、当院と連携する高度医療機関をご紹介いたします。
狭心症と心筋梗塞の違い
心筋梗塞が狭心症と最も異なる点は、冠動脈が閉塞を起こして心筋が壊死しているか、していないかです。狭心症の場合は、冠動脈が狭窄を起こしている段階のため、血流そのものは維持され、心筋が壊死することはありません。しかし、心筋梗塞の場合は、冠動脈が完全に閉塞を起こして血流が遮断されるため、心筋に酸素が運搬されなくなって壊死します。なお、一度壊死した心筋は再生することはありません。狭心症のタイミングで治療できれば、心臓の機能は維持されますが、心筋梗塞で治療した場合は、心臓の機能は低下したままとなります。その他、狭心症の症状は比較的短時間で治まるのに対し、心筋梗塞は激しい痛みが突然現れ、長時間持続する傾向があります。
虚血性心疾患の予防
虚血性心疾患の主な原因は生活習慣の乱れのため、生活習慣を改善することが予防には最も大切です。具体的には、食事習慣の改善や適度な運動習慣の取り入れ、禁煙などを行います。
食事習慣の改善
食事では、塩分や脂質の摂りすぎに注意しましょう。塩分の過剰摂取は高血圧の原因となり、動脈硬化を引き起こして虚血性心疾患の発症リスクを高めます。
なお、日本高血圧学会では、6g/日を超える塩分を摂取すると、動脈硬化のリスクが高まると報告されています。そのため、塩分の摂取は6g/日未満を心がけましょう。
また、脂質の多い食事習慣を続けると、血液中のコレステロール量が増大して動脈硬化を引き起こします。そのため、脂身の多い牛肉や鶏肉などの飽和脂肪酸、揚げ物、生クリームの過剰摂取も控えるようにしましょう。
適度な運動
運動不足は、虚血性心疾患の発症リスクを高めます。そのため、適度な運動習慣を取り入れることは、虚血性心疾患を予防する上で大切です。
運動は継続が大切です。最初は無理のない範囲で軽いウォーキングやジョギング、水泳などから始め、長期間継続することを心がけましょう。
禁煙
喫煙習慣は虚血性心疾患の発症リスクを高めます。実際に、1日1箱以上の喫煙習慣がある人は、ない人に比べて虚血性心疾患の発症リスクが男性では2~4倍、女性では7倍高まることが報告されています。一方、1年間禁煙すると、虚血性心疾患による死亡率が半分まで低下することも報告されています。
心臓リハビリテーションとは
 心臓リハビリテーションとは、狭心症や心筋梗塞の治療、心臓の手術などを行った患者さまに対して、退院後の再発を予防するために、様々なフォローアップを行う医療サービスです。
心臓リハビリテーションとは、狭心症や心筋梗塞の治療、心臓の手術などを行った患者さまに対して、退院後の再発を予防するために、様々なフォローアップを行う医療サービスです。
虚血性心疾患を発症した患者さまは、心臓機能が健常者と比べて低下していることから、退院後も食事療法や運動療法を行って再発を予防する必要があります。
心臓リハビリテーションでは、専門の医師や看護師が患者さまの生活スタイルや症状の程度を考慮し、患者さま一人一人に対して適切な食事習慣の改善指導や運動療法、禁煙指導などをご提案いたします。
当院でも体制を整えていく予定ですので、開始する際はお知らせいたします。